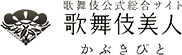「ニューヨークを飲み込んだアンチヒーロー」第4回
グッドニュースは明け方に
ニューヨークで役者や演出家を殺すのは簡単だ。ペンと紙さえあればいい。
大小無数の劇場がひしめき合い、常に新作が上演されるこの街の劇評家は決して俳優や演出家に媚びたりしない。劇評が悪ければ、2?3日で公演が打ち切りになるのもオーバーな話ではない。
「コメディーを上演すれば、ニューヨーカーたちも『日本から来た伝統芸能』とは観てくれない。厳しい判断をされる可能性もある。だけど、52歳の今だから、失敗してもまだ大丈夫だと思った」
ニューヨークで中村勘三郎は、東京からずっと抱え続けていた胸の内を語ってくれた。それでも前回の評価を超えるためには『法界坊』を演るべきだと思った。
7月19日。ニューヨーク公演の幕が開いて3日目の朝。勘三郎は朝早く目覚め、部屋に新聞が届くのを待っていた。この日の芸術欄に中村座の劇評が載ると前日から聞いていた。届いた二つ折りの新聞紙を開く。一面の下に歌舞伎の写真が載っていた。だがそれは中村扇雀と片岡亀蔵の写真。
「法界坊じゃないんですよ。載ってるのが。俺の芝居はうけなかったのか...と思って、ガックリしてね。新聞を置いてもう一回寝たんです」
でも、どうしても気になって眠れない。意を決して起き上がり、芸術欄を開いた。するとそこには!誌面の半分を埋め尽くす大喜利の場面の写真が。
「やった!って思って、今度は逆に興奮して眠れなくなっちゃってね。朝の6時前ですよ。しかもその記事を書いた劇評家は、ニューヨークでもめったに芝居を褒めないので有名な人だって後から聞いて、本当に嬉しかった」
勘三郎をそこまで興奮させたのは単に舞台の評価が良かったからではない。劇評家のチャールズ・イシャーウッドの原稿は、まさに今回"賭け"と思われた『法界坊』の演出意図を的確に汲み取っていた。
法界坊という人物像は、いい意味で歌舞伎特有のハチャメチャ感に満ちている。前半は欲に支配されたコミカルな堕落坊主。だが二幕目の「三囲土手の場」で自分の命が危うくなると、人格が豹変したかのように二人の登場人物を残忍に斬り殺す。
劇評は「法界坊のキャラクターが極度に変化するのは西洋人にとって不愉快ではない」とし、欲に正直でコミカルな法界坊と、悪に憑かれた霊を力強く表現する様は「俳優の業とは、畏れに近いものだと思い起こさせてくれる」と論じた。平成中村座は歌舞伎本来のルーツと本来はない「演出」という新たなエネルギーとの融合で生まれている、と。
演出の串田和美は劇評を読んで「自分が稽古で言ってることがそのまま書かれていてビックリした。この人、稽古の時、こっそり観てたんじゃないの!って(笑)」
欲望の限りに生き、最期は斬られて自分の掘った穴に落ちて死ぬ法界坊。諦めきれずのたうちまわる魂と、浄化。その姿に観客は自分が抱える闇や葛藤をジリジリと感じながら、最後は共に解き放たれる。日本人も、外国人も同じ。
「昨年のコクーンの『東海道四谷怪談』、今年の『三人吉三』そして『法界坊』。
主人公や登場人物のほとんどがみんな奈落に落っこちて行くようなイメージがあるんですよ。人間には、一生懸命生きているのに『こんなはずじゃ...』と思いながら自分自身や世の中が壊れていくのを受け入れる業がつきまとうんじゃないか」その業を描きたいという気持ちが、ここ数年どんどん強くなっていくと串田和美は語る。
平成中村座が生み出した法界坊。彼は220年間、いろいろな姿を借りてこの世に生き続けている。闇と浄化。人が生きる限り、存在するもの。
21世紀のニューヨークに住む辛口劇評家の絶賛コラムに、法界坊の霊魂は今度こそ納得して成仏するのだろうか。それとも悪態をついて、まだまだこの世界に居座り続けるのか。
富樫佳織(放送作家)