
【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
演じ手の美意識が投影された衣裳
|
|
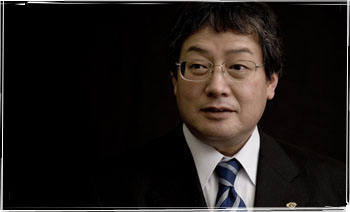 |
20歳で入社され、今年で30年目になるという宮永晃久さん。三代目實川延若を担当した後、ご指名によって坂田藤十郎(担当当初は扇雀)の担当に。三代目中村鴈治郎襲名、四代目坂田藤十郎襲名と、2つの襲名にも立ち合われたそうだ。 |
|
|

 |
草木染で江戸紫に染められた『鷺娘』の衣裳。舞台の照明は想像以上に衣裳にダメージを与えるらしく、毎日舞台で用いれば半月で色あせが生じてくるという。 江戸紫の衣裳を引抜いた後は、浅葱(あさぎ)色に変化する。 どちらも鷺の柄だが、こちらは舞い降りるイメージの図案となっている。 |

出番を待つ衣裳の数々。縫製課で仕立て上げられ舞台へ出て行く。
|
|
|
|
|
歌舞伎の舞台には、多様な役柄の人物がそれぞれにふさわしい衣裳を着て登場します。贅を尽くした豪華な道中着姿の花魁、凛とした裃(かみしも)をまとった武士、はたまた溌剌とした町衆の半纏(はんてん)姿。それらの姿、身のこなしを見ていると、日本人の身体を最も美しくみせるのは、やはり和服だと痛感させられます。
今回は、その歌舞伎の衣裳に注目したいと思います。お話をうかがうのは、松竹衣裳株式会社 営業本部演劇部部長の宮永晃久さんです。舞台で使用している衣裳を特別にご準備いただいたのですが、実際に触れてみると予想以上にずっしり。かなり重く感じられました。
「新素材を使えば、もっと軽くすることもできるんです。役者さんと相談して、いろいろ工夫したこともあるんですけど、舞台に出て動いてみると、ふわふわしちゃって重みが出ないというか、やはり様にならないんです。それに舞踊などではある程度の重みがあるほうが、裾さばきもよく踊りやすいということもあるようです。
同じ演目の同じ役柄であっても、役者さんによって解釈や演じ方は異なりますよね。その意向に合わせて衣裳も色や図案がちがってくるんですよ。たとえば『鷺娘』では、引抜きによってさまざまに衣裳が変化していきますが、ある役者さんはその中の1枚には鷺が飛び上がるイメージ、もう1枚には舞い降りるイメージを思い描いておられました。それを具体的な衣裳という形にするのが仕事ですから、私たちも演目を深く理解し、役者さんの美意識を汲み取れるようになっていなければならないんです」
俳優さんの精緻な美意識が織り込まれている衣裳。こうした魂のこもった衣裳があるからこそ、演じる役のリアリティが伝わってくるのかもしれません。
今回は、その歌舞伎の衣裳に注目したいと思います。お話をうかがうのは、松竹衣裳株式会社 営業本部演劇部部長の宮永晃久さんです。舞台で使用している衣裳を特別にご準備いただいたのですが、実際に触れてみると予想以上にずっしり。かなり重く感じられました。
「新素材を使えば、もっと軽くすることもできるんです。役者さんと相談して、いろいろ工夫したこともあるんですけど、舞台に出て動いてみると、ふわふわしちゃって重みが出ないというか、やはり様にならないんです。それに舞踊などではある程度の重みがあるほうが、裾さばきもよく踊りやすいということもあるようです。
同じ演目の同じ役柄であっても、役者さんによって解釈や演じ方は異なりますよね。その意向に合わせて衣裳も色や図案がちがってくるんですよ。たとえば『鷺娘』では、引抜きによってさまざまに衣裳が変化していきますが、ある役者さんはその中の1枚には鷺が飛び上がるイメージ、もう1枚には舞い降りるイメージを思い描いておられました。それを具体的な衣裳という形にするのが仕事ですから、私たちも演目を深く理解し、役者さんの美意識を汲み取れるようになっていなければならないんです」
俳優さんの精緻な美意識が織り込まれている衣裳。こうした魂のこもった衣裳があるからこそ、演じる役のリアリティが伝わってくるのかもしれません。






