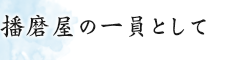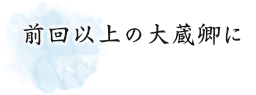【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
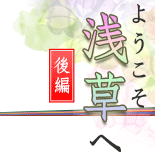

――第1部『一條大蔵譚』で歌昇さんは、一條大蔵卿長成をなさいます。平成24(2012)年12月に勉強会の「伝統歌舞伎保存会研修発表会」で初演された役への、本興行初挑戦になりますね。
浅草歌舞伎に出るときは大蔵を演じたい、播磨屋のおじさん(中村吉右衛門)の出し物を演じさせていただければと思っていたのでうれしいです。
――以前、吉右衛門さんに教わられた内容を書き込んだ台本を見せていただいたことがあります。
2年前の公演後、ずっとさらっていました。せりふも鮮明に覚えています。今回の上演も、前の場面の「檜垣」がないので、大蔵卿が世間に対して阿呆でいるとわかる箇所がありません。最初から本心をさらけ出した状態で出てきますので、導入が難しいと思います。
浅草歌舞伎の一翼を担い、なおかつ播磨屋の“家の芸”である大蔵卿を、播磨屋の一員として1カ月勤める…。そこも僕にとっては意義があるし、大事です。お客様に歌昇という役者を見ていただくと同時に、おじさんの芸をちゃんと教わっていると思われたい。
――どんな大蔵卿になさりたいですか。
どんな方にも魅力的に思っていただける大蔵卿でありたいです。おじさんには、大蔵卿はあくまでもお公家さんでいないといけない、下品にならないように意識しなさいと言われました。前回以上に公家らしくできればと思っています。
――歌昇さんの考えられる公家らしさとはどんなものですか。
言葉に丸みがあり、張っているのにとがらない。それが、上品に聞こえる…。優雅に見せようとも思っています。おじさんは大蔵卿には播磨屋の芸の要素が詰まっているとおっしゃいました。つくり阿呆をしてこなければいけなかった悲壮感がある。源氏復興のために、隠し通し続けてきた、その内面を少しでも出せないといけないと思います。
――正気からつくり阿呆への切り替えが、一つのみどころになります。
変わり目が難しいです。大蔵卿はそれを普通にこなしてきた人なので、ぱっと切り替えることもできたのでしょうが、前回の僕にはできませんでした。大蔵卿の心が自然ににじみ出るようにしたい。20年間、周囲を欺き続けるのには気持ちの強さがあったはずです。さらに、最後はつくり阿呆に戻る悲しさを見せなくてはいけません。どこまで行っても自己犠牲の人です。
――演じられる前と演じられた後で、印象が変わられたことはありますか。
演じる前は、衣裳がぶっ返った後のきまりは格好いいし、さぞ気持ちのいい役だろうと思っていましたが、演じてみるとこれだけ苦しい役はない。どこまで行っても幸せにはなれない人です。自分の才能をすべて隠している…。才能を活かせないのは、どんな感覚なんだろうと思いました。演じる前と後で、そこが一番違いました。
――それでも、苦しい大蔵卿をなさりたいと思ったのは?
やはり好きだからです。『菅原伝授手習鑑』の梅王丸や『義経千本桜』の忠信のような、荒事の明るい役も好きですが、大蔵卿のように自分を追い詰め、肚(はら)で勝負する役を今後も勉強していきたいです。

お年玉<年始ご挨拶>出演日
2日(金) 3日(土) 4日(日) 5日(月) 6日(火) 7日(水) 9日(金) 10日(土) 11日(日) 13日(火) 14日(水) 15日(木) 16日(金) 17日(土) 19日(月) 20日(火) 21日(水) 23日(金) 25日(日) 26日(月)
出演演目
『一條大蔵譚』一條大蔵長成/『仮名手本忠臣蔵』不破数右衛門/『俄獅子』鳶頭
四代目 中村歌昇
(なかむら かしょう)
| 生まれ | 平成元年5月6日、東京都生まれ。 |
|---|---|
| 家族 | 三代目中村又五郎の長男。初代中村種之助は弟、五代目中村米吉はいとこにあたる。 |
| 初舞台 | 平成6年6月歌舞伎座『道行旅路の嫁入』旅の若者で四代目中村種太郎を名のり初舞台。 |
| 襲名 | 平成23年9月新橋演舞場『菅原伝授手習鑑』「車引」舎人杉王丸、「寺子屋」涎くり与太郎、『舌出三番叟』千歳、『勢獅子』鳶頭雄吉ほかで四代目中村歌昇を襲名。 |

お年玉<年始ご挨拶>出演日
2日(金) 3日(土) 4日(日) 5日(月) 6日(火) 7日(水) 9日(金) 10日(土) 11日(日) 13日(火) 14日(水) 15日(木) 16日(金) 17日(土) 19日(月) 21日(水) 22日(木) 23日(金) 25日(日) 26日(月)
出演演目
『一條大蔵譚』常盤御前/『独楽売』芸者/『俄獅子』芸者
五代目 中村米吉
(なかむら よねきち)
| 生まれ | 平成5年3月8日、東京都生まれ。 |
|---|---|
| 家族 | 五代目中村歌六の長男。四代目中村歌昇、初代中村種之助はいとこにあたる。 |
| 初舞台 | 平成12年7月歌舞伎座『宇和島騒動』武右衛門倅(せがれ)武之助で五代目中村米吉を名のり初舞台。 |

お年玉<年始ご挨拶>出演日
8日(木) 12日(月・祝) 18日(日) 20日(火) 22日(木) 25日(日)
出演演目
『春調娘七種』静御前/『一條大蔵譚』お京/『仮名手本忠臣蔵』おかる/『俄獅子』芸者
六代目 中村児太郎
(なかむら こたろう)
| 生まれ | 平成5年12月23日、東京都生まれ。 |
|---|---|
| 家族 | 九代目中村福助の長男。 |
| 初舞台 | 平成11年11月歌舞伎座『壺坂霊験記』観世音で本名で初お目見得。12年9月歌舞伎座『京鹿子娘道成寺』所化知念坊、『菊晴勢若駒』春駒の童で六代目中村児太郎を名のり初舞台。 |
※青字は第1部、赤字は第2部
ようこそ浅草へ
-

ようこそ浅草へ「新春浅草歌舞伎」、三年目の挑戦 後篇
若手の登竜門といわれる「新春浅草歌舞伎」は、芝居に対する“熱”はどこの劇場にも負けないと、毎年、新鮮な舞台を見せています。でも、それだけではありません。中心となる出演俳優が一気に世代交代して3年目の今回は「ステップアップした私たちをご覧いただけるように」と、それぞれが強い気持ちで挑みます。後篇も公開!
-

ようこそ浅草へ「新春浅草歌舞伎」、三年目の挑戦 前篇
若手の登竜門といわれる「新春浅草歌舞伎」は、芝居に対する“熱”はどこの劇場にも負けないと、毎年、新鮮な舞台を見せています。でも、それだけではありません。中心となる出演俳優が一気に世代交代して3年目の今回は「ステップアップした私たちをご覧いただけるように」と、それぞれが強い気持ちで挑みます。
-

ようこそ浅草へ――後編
自分たちが新しい浅草歌舞伎の幕を開ける! 熱意を舞台にぶつけ、一人でも多くのお客様に楽しんでいただきたいと奮闘する三人が、演じる役のことを語る後編です。