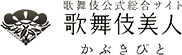歌舞伎にまつわる読み物コンテンツを紹介する「歌舞伎の記憶」。
今回は、コロナ禍の演劇界に焦点を当て、「コロナ禍に立ち向かう歌舞伎」と題して、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の後藤隆基助教にご寄稿いただきました。約100年前に流行したスペイン風邪と今回の新型コロナウイルス。時代も環境も異なる2つのパンデミックを比較し、演劇の灯を消さぬよう模索し続ける歌舞伎界、演劇界の、次の時代へとつながる軌跡を綴ります。
コロナ禍に立ち向かう歌舞伎
文/後藤隆基(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 助教)
構成/歌舞伎美人編集部
令和2(2020)年2月26日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止措置として、安倍晋三首相(当時)が大規模イベント等の開催自粛を要請しました。俗に「令和の2.26事件」とも称されたあの日は、21世紀の文化史上、忘れえぬ日付として記憶されるでしょう。
多くの劇場がただちに公演の中止や延期を発表。新型コロナウイルスの正体も対策も判然としない段階で、演劇界は急な対応を迫られました。混迷の3月を経て、4月7日に最初の緊急事態宣言が発出。演劇の時間は、数カ月にわたって止まってしまいます。5月25日に全国で宣言が解除されると、さまざまな制約のなか、誰もが薄氷を踏むような思いで、再び時計の針を動かしはじめたのです。
文字どおり未曾有の事態に見舞われた2020年以降、コロナ禍の比較対象として話題に上ったのが、約100年前の「スペイン風邪」です。大正7(1918)年から大正10(1921)年頃、世界中に蔓延したパンデミックによって、全人口の3~5%にあたる5,000万人以上が犠牲になりました。日本にも三度の流行の波が上陸し、当時の人口5,500万人のうち約半数が罹患、1%近くの約50万人が亡くなったといいます。大正12(1923)年の関東大震災の死者が約10万人ですから、5倍以上の犠牲者を出したことになります。

スペイン風邪は、演劇界にも影響を及ぼしました。被害が少なかったといわれる流行の第一波――大正7年5月から7月頃にも、東京見物を兼ねた巡業中の宝塚少女歌劇団をスペイン風邪が襲い、劇団員や引率の教師らが次々に感染しています。同年秋から感染が急拡大し、翌春にかけて第二波が到来。渦中の大正7年11月、宝塚少女歌劇団内の集団感染で若い命を落とす劇団員もいました。また、劇作家で演出家の島村抱月率いる芸術座では、二世市川猿之助ら歌舞伎俳優との合同公演の稽古中、看板女優の松井須磨子が罹患。須磨子はまもなく快癒しますが、同棲していた抱月も感染し、発症からわずか一週間後の11月5日に肺炎を併発して泉下の人となりました。抱月の死と、その2カ月後に須磨子が後追い自殺を遂げたことは、スペイン風邪が演劇界にもたらした最大の悲劇といえるでしょう。
歌舞伎界にも、スペイン風邪は襲いかかります。帝国劇場の技芸委員長(座頭)だった六世尾上梅幸は、大正7年の暮れに罹患し、年明けの初春興行の稽古に出られない状態が続きました。主治医の勧めで梅幸は休演を決断、出演予定の演目は代役を立てて急場をしのぎますが、その後も体調すぐれず、横浜に転地療養するも肺炎を併発。歌舞伎座の2月興行に参加を予定していたものの断念し、本復まで時間がかかりました。
第三波が襲った大正8(1919)年末には、十一世片岡仁左衛門が妻とともに高熱の枕を並べ、歌舞伎座の初春興行の初日を延期する事態になりました。幕が開いてからも40度近い高熱で舞台に立ち続けて「舞台を戦場の俳優の鑑」(「編輯日誌」『新演芸』大正9年2月)といわれますが、出番の『近頃河原達引 堀川』のあばら家の場面では屏風の影に電気ストーブを置いていたそうですから、相当無理をしていたのでしょう。どうにか興行を終えると、2月の歌舞伎座を休演。予後の経過を案じたのかもしれません。
仁左衛門が病魔に冒されていた大正9(1920)年1月、帝国劇場の脚本主任で、河竹黙阿弥の系譜を引く作家と評された右田寅彦が、発症後に肺炎を併発して11日に死去。右田家は一家全員が感染しており、感染力の強さがうかがえます。同年6月2日には、初世中村鴈治郎の門弟中村林若が亡くなっています。
夏に一度落ち着きをみせるも、秋や冬から翌春に復活というパターンでウイルスは変異し、流行をくり返しました。三度の波が去ったあとも、完全には収束しません。大正11(1922)年1月、十五世市村羽左衛門が、高熱とひどい咳をおして新富座に出演したのも一例。主治医は休演を勧めますが、縁起のいい初芝居だからと、羽左衛門は舞台に立ち続けました。梅幸、仁左衛門、羽左衛門…。時期は異なるものの、それぞれ流行の只中にあった年末から年明けに感染し、重症化したようです。
では、スペイン風邪の流行下、劇場はどのような感染対策を講じていたのでしょうか。注意すべきは、劇場は平時と同様、扉を開けていたという事実です。大正7年秋に「新庁令で各座が空気抜きの煙管の親分見た様なものを屋上へ附着け」(「演芸風聞録」『東京朝日新聞』11月4日)るなどの換気対策がみられますが、劇場や人の集まる施設への休業要請等の措置はとられていませんでした。帝国劇場では、大道具スタッフの半数以上が風邪で倒れたために幕間が延びたという報道もあり、楽屋裏で感染がひろがっていた可能性も否めません。
パンデミックの渦中に劇場が開いていたのか…と驚かされるのは、私たちが、コロナ禍によって劇場が扉を閉ざし、膨大な数の公演が失われてしまう事態を目の当たりにしたからに他なりません。出演者やスタッフの感染、世界的流行と海外からもたらされた疫禍であることなど、スペイン風邪とコロナ禍は共通点も散見します。時代や環境の異なる2つのパンデミックを単純に比較できませんが、大正期の記録をみると、現代に比べて医療技術や知識が充分ではない時代に、目に見えない疫病への恐怖を感じながらも対応を模索していた様子がわかります。約100年の時を経て、今日の演劇界は、最新の知見や情報を駆使し、かつて経験したことのない難局に立ち向かうことになりました。
歌舞伎座は、令和2年3月から5カ月の空白を経て「八月花形歌舞伎」で再開の狼煙を上げました。前例のない四部制を敷き、各部で場内を完全に入れ替えて消毒、出演者やスタッフも他の部の関係者とは顔も合わせない。観客の入場時の検温や手指の消毒、マスクの着用をはじめ、筋書の販売やイヤホンガイドの貸出を一時休止しました。入場者数の制限が解除されて100%収容が可能になっても、客席配置を工夫して50%の体制を維持。令和3(2021)年1月から三部制にシフトチェンジしてからも、厳しい対策を徹底して事態に臨んでいます。






(「Lost in Pandemic ――失われた演劇と新たな表現の地平」展示より)
客席における感染対策はもちろん、普段我々の目に触れることがない楽屋や舞台裏での対策も徹底して行われています。昨年8月の公演再開に際しては、楽屋口での検温や消毒液の設置など基本的な感染対策はもちろん、歌舞伎の舞台裏ならではの習慣も見直しを図られました。楽屋到着時に出演者が出勤したことを示すために、自分の名前の上に棒を刺す着到盤は現在、頭取(楽屋の事務担当)が棒刺しを代行しており、またその脇に設置されている「清めの塩」は撤去、楽屋係による履物の取り扱いも行われていません。歌舞伎の楽屋では当たり前の光景である挨拶まわりも禁止され、舞台袖では特に会話が制限されています。

アルコール消毒が困難である歌舞伎の衣裳や鬘、小道具などに対しては、市販の殺菌スプレーによる消毒なども検討されたそうですが、生地を傷める恐れもあり、病院内消毒で使用されている紫外線を用いた除菌機材を導入しています。また、感染症の専門家監修のもと、感染リスクの高い演技や舞踊の振付などを一つひとつ検証し、出演者の不安の払拭にも努めたそうです。さらに出演者・スタッフが安心して舞台に出演し、体調不良時にもすぐに申し出ることができるよう、丁寧な説明やヒアリングでメンタル面でのフォローも徹底したといいます。公演再開以降、全体稽古が行われる前に翌月の公演関係者はPCR検査を受け、全員が陰性であることを確認したうえで毎月初日を迎えている歌舞伎座ですが、現在も、クラスターの発生事例や最新情報をこまめに確認し、劇場内の感染対策のアップデートを欠かすことはありません。
こうした感染対策は、令和2年の劇場再開時――今にして思えば“序盤戦”にあたる時期に、歌舞伎座のみならず、演劇界全体が試行錯誤の果てにたどり着いたものです。それらを土台に絶えず更新しながら、コロナ禍との戦いを続けています。そして、今も模索されている幾多の試みが、次の時間へとつながっていくのでしょう。
スペイン風邪から約100年。コロナ禍という新たな災厄のなかで、2020年代の幕が開きました。過去から何を学びうるかという問いは、私たちが未来に何を残せるかという問いに直結します。苦境に立つ演劇界の軌跡は、数世紀後を照らす光になるはずです。
後藤 隆基(ごとう りゅうき)
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 助教、昭和56(1981)年静岡県生まれ。
立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士後期課程修了。博士(文学)。専門は近現代日本演劇・文学・文化。著書に『高安月郊研究――明治期京阪演劇の革新者』ほか。演劇博物館オンライン展示「失われた公演――コロナ禍と演劇の記録/記憶」および2021年度春季企画展の企画を担当。
現在、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館では、2021年度春季企画展「Lost in Pandemic ――失われた演劇と新たな表現の地平」を開催中です。コロナ禍によって失われた公演/失われなかった公演や、新たな表現の可能性に光をあてるとともに、過去の疫病や感染症を演劇がどう描いてきたかを示す館蔵資料を発掘・紹介。新型コロナウイルスが社会や演劇界に与えた影響をまとめた年表や、演劇の灯を消さないために実践された対策や試みを紹介しています。ぜひお立ち寄りください。