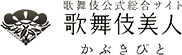歌舞伎文様考

『京鹿子娘道成寺』白拍子花子の衣裳

『菅原伝授手習鑑』「賀の祝」桜丸の衣裳。擦り切れた肩や袖などに別の布を接いで、貧しさを表した肩入(かたいれ)の衣裳。肩入れは落ちぶれた者や浪人などの役柄に用いられる。

『菅原伝授手習鑑』「賀の祝」桜丸。三世歌川豊国画 文久元年 (1861年)。現在の歌舞伎衣裳と、色は異なるが桜の柄の別布を接いだ様は同様。 早稲田大学演劇博物館蔵。無断転載禁©The TsubouchiMemorial Museum, WasedaUniversity, All Rights Reserved.
儚さを愛でる日本人の感受性
歌舞伎は江戸の庶民生活と融合し、四季の移り変わりとともに興行を繰り返してきました。観客は自然のリズムが歌舞伎小屋を支配していることを知り、舞台上に一足早く訪れる春夏秋冬を感じながら、四季の移ろいを確かめたのです。中でも桜の文様はおそらく、歌舞伎で最も多く用いられる文様のひとつでしょう。
古くは古事記や日本書記、万葉集にも登場するその華やぎや艶やかさは、「花」と言えば桜を指すほど日本人に親しまれ、心身に深く染み透っています。
平安時代になると桜花の宴や桜会といった催事が盛んに行われ、衣服や什器にも桜文様は広く使われるようになりますが、本格的に庶民の文様となるのは江戸時代以降のことです。
江戸っ子にとって春の花見は欠かせない行事となり、満開の華やかさと散り際の鮮烈さ、流水に流れる様などが、意匠の限りを尽くし精緻に文様化されるようになります。
歌舞伎の世界で使われている桜で最も艶やかなのは、舞台全景が桜で覆われる『京鹿子娘道成寺』でしょう。枝垂桜文様が大きくあしらわれた白拍子花子の衣裳の地色が、赤、浅葱、藤色などと次々変わる演出で、まるで映画の残像効果のように清姫の亡霊である花子の幽幻なイメージが心に強く残ります。
また桜文様が物語の結末を暗喩する演目もあります。
『菅原伝授手習鑑』の桜丸は、着物や大小の刀にも桜が散りばめられた美しい装束が目を惹きます。この桜丸は主君である斎世親王と菅原道真の養女、苅屋姫との恋を取り持ちますが、駆け落ちが道真の流罪につながってしまった責任を取り切腹する運命を辿ります。自害直前に桜丸が纏うのは、紫地に白抜きの清浄な桜文様の衣裳。ここでの桜は死と結び付き、悲嘆や哀惜の花として儚さや切なさを観る人に訴えます。日本の国花でもある桜、歌舞伎にはそのエッセンスが凝縮しています。
歌舞伎文様考
バックナンバー
-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂
『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。
-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様
今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。
-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)
前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)
話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第10回 和事衣裳の文様と色彩
今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。
-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く
今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。
-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様
今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。
-

第7回 旅する「唐草模様」
数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。
-

第6回 役者紋を纏う
俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。
-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様
日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。
-

第4回 “演技する”文様
十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。
-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話
武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。
-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様
歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。
-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース
歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。