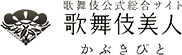江戸職人(クラフト)手帖
 |
 |
 |
||
おりがみ会館の中にある工房 |
黒い縞模様を絵付けしている小林さん |
無地の色折り紙を染めている萩原さん |
職人の手に宿る、江戸のものづくり
東京・湯島にあるおりがみ会館。千代紙で作られた人形などの作品を展示する1階ギャラリーを入り上の階に通されると、眼をみはる光景が広がります。ビルの中に、千代紙を手染めで作る工房が入っているのです。
「顔料こそ色落ちに強い化学染料を使うようになりましたが、染めの技術は昔から変わりません。染料を含ませた刷毛で1枚、1枚、職人が染めています」
取材当日に職人さんが作業をしていたのは、黄金色の地に黒い縞模様が入った千代紙です。大胆でインパクトのある図柄です。
「これは来年の干支の寅柄です。折り紙で寅を作ると、ちょうどいい感じで柄が出るんですよ。歌舞伎衣裳に代表される江戸文様はもちろん、十二支の文様や友禅文様など江戸千代紙のデザインは多岐に渡ります」
工房の天井には30センチほどの感覚で縄が貼られていて、職人さんは地色を染めた紙を専用の棒を使って1枚ずつかけていきます。午前中いっぱいで天井を埋め尽くすくらいの紙を染めて、およそ100枚。かけるところがなくなったら、ちょうど最初に染めた紙が乾燥する頃合いだと言います。
「刷毛の減り方を見れば職人の腕がわかると言われています。色むらなくしっかり染める職人の刷毛は、減り方が平行なんです」
色別に美しく仕分けされた刷毛を見ると、新しいものと使い込んだものは一目瞭然です。紙の上を滑らせるだけでも、何千枚、何万枚と作業を繰り返すうちに毛が摩擦ですり減っていくのです。
「いい千代紙に必要なのは染め職人の腕はもちろん、道具を作る職人の腕も重要です。この刷毛だって減りはするけれど、おかしな方向に反ったり曲がったりは絶対しないんですよ。紙を漉く職人、刷毛を作る職人、そして版木を作る職人、ひとりでも欠けたら江戸千代紙を残していくことができなくなるんです」
小林さんは工房で使い続けている手作りの道具を見せてくださいました。
「これは『種木(しゅもく)』といって、染めた紙を天井の縄にかけるための棒です。使ううちにどんどんすり減って短くなっていくんですよ」
刷毛が減るのもさることながら、紙をかけるための木材がすり減るのは驚きです。途方もない枚数を職人が1枚1枚染め上げた証です。
かつて顔料を砕くために使っていた巨大なすり鉢、千代紙の上に不規則な点模様を作るための箱形の道具、ひとつひとつが職人の鍛錬と知恵を物語ります。
 |
|
上:色とりどりの染料が付いた刷毛 |
 |
 |
 |
左:上2本が種木(しゅもく)。細くて黒い方が何年も使い込まれたもの。下2本は染料をかき混ぜる撹拌棒。こちらもすり減っている上にある方が使い込まれたもの。
右:種木を使って、染めた紙を天井の縄にかけているところ
 |
 |
|
小林さんが「パタパタ」と呼ぶ道具はその名の通り、上下に振ると歯ブラシのような部分がパタパタと上下して染料を飛ばしながら点を作る。戦後に作られたもの。 |
江戸職人手帖
バックナンバー
-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~
役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。
-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~
向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。
-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜
東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。
-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜
東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。
-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~
勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。
-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~
一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。
-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜
江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。
-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜
第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。