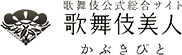江戸職人(クラフト)手帖
職人人生70年― 技と芝居とともに生きる
 |
西山鴻月さん |
 |
鴻月さん作『暫(しばらく)』より。紅の筋隈(すじくま)、力紙をつけた車鬢の鬘(かつら)でおなじみ。荒事を代表するヒーロー、鎌倉権五郎。 |
江戸に生まれた押絵羽子板の技を受け継ぐ西山鴻月さんは今年88歳。15歳で羽子板の面相師である倉田雅生氏の元に弟子入りして以来、技を磨き続けてきました。
「私は幼い頃から絵を描くのが大好きで、時間があると手を動かしていました。それを知っている近所のおじさんがある日『羽子板の面相師を探しているところがあるから行ってみないか』と話を持ってきてくれたんです。話を聞いてすぐ師匠の家に行きまして、弟子入りしたのがこの道に入ったきっかけです」
当時の職人は、手取り足取り仕事など教えてはくれません。当然、師匠の仕事を「見て学ぶ」日々が始まりました。自分にできることを探し、着物の模様を描くことから、小道具の扇子、『汐汲(しおくみ)』の羽子板に欠かせない桶を作るといった小さな仕事からコツコツと身につけていったそうです。芝居との出会いは―
「弟子入りをして初めての正月に、師匠の家で初めて『演芸画報』という雑誌を見せてもらいましてね。そこに載っている歌舞伎俳優の姿に目を奪われました。それで『芝居を観なきゃ仕事にならない』と決意して、小遣いをはたいて歌舞伎を観に行ったんです。電車賃がもったいないから浅草から東銀座の歌舞伎座まで歩いて行きました」
昭和12年。初めてその目で観た舞台は『二條城の清正』。初代中村吉右衛門の加藤清正、二世市川左團次の徳川家康、十七世中村勘三郎の豊臣秀頼という配役でした。
「眼の前の役者の迫力にとにかく圧倒されました。押絵羽子板は、衣裳をつけた役者の姿をデザインしてきれいに作ればいいというものではないんです。役者の凛とした姿、役を演じる時の気迫、心に伝わって来る役の魂を限られた板という空間に凝縮して初めて形になります。ですから歌舞伎を一生懸命観て、役柄の細かい心の動きを自分の中に刻み込まなければ作ることはできません。『勧進帳』の弁慶を作るなら、上手に富樫がいて、下手には義経がいる情景が目に浮かぶように。自分自身が弁慶の気持ちで作って初めて役者の姿になるのだと思います」
2年前の9月、鴻月さんは東京の歌舞伎座で二代目中村吉右衛門演じる『二條城の清正』をご覧になり、その年の羽子板に清正の姿を写しました。
「芝居を観ていたら、自分が初めて芝居で観た先代の姿が瞼に浮かんできましてね。あぁ、芸というものはこうして人から人へと伝承してずっと命を持ち続けるのだなあという思いがこみ上げてきました。羽子板に、人から人へと伝わる芸の凄み、そして自分が初めて歌舞伎を観た、駆け出しの頃から70年の年月を映すことができたら、という気持ちで作りました」
一尺五寸(約45cm)の板に写された役者の姿。それは芝居を観る職人の感性と、その心を揺さぶる歌舞伎の魂が融合して生まれるのです。
 |
左:「昭和舞台姿 その六」「清正 中村吉右衛門丈」太田雅光画。
|
江戸職人手帖
バックナンバー
-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~
役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。
-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~
向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。
-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜
東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。
-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜
東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。
-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~
勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。
-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~
一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。
-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜
江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。
-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜
第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。