ニュース
勘九郎、七之助が語る、歌舞伎座『きらら浮世伝』

2025年2月2日(日)に開幕した歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」昼の部『きらら浮世伝』に出演する中村勘九郎、中村七之助が、演出の横内謙介とともに公演に向けての思いを語りました。
▼

37年越しに上演する意味
37年前に銀座セゾン劇場で上演された本作を、今回は歌舞伎として装いも新たに上演します。まず勘九郎が、「稽古も進み、七之助と“いい作品になる”という手ごたえを感じています。公演が近づき、出演者の皆さんとの稽古も佳境に入りました。皆様に少しでも楽しんでいただけるよう作品をつくっていますので、どうぞご期待ください」と、にこやかに話します。
続いて七之助も、「読み合わせから始まり、毎日のように稽古を行っていますが、近年の新作に負けず誇れる作品になると思います。これからさらに化学反応が起きて、素晴らしい作品になっていくと感じています。せりふや音楽など、今の段階でも胸にぐっとくる場面が多く、歌舞伎座で上演する意味も日々感じていますので、これは自信作になると思います」と、稽古での手ごたえを語りました。
演出を勤める横内は、「37年前は(十八世中村)勘三郎さんが体当たりで上演し、お客様の熱気も感じる舞台でした。“蔦重”が生きた寛政の改革の時代は、贅沢禁止が掲げられ、庶民への弾圧があった時代。ある意味コロナ禍に我々も体験した、文化芸術が不要不急と言われた感覚に似ているのかもしれません。江戸時代にも、文化によって命を救われ、生きる楽しみとした人は大勢いたはず。37年を経て、コロナ禍を経験した今、上演する意味を強く感じています」と、上演するうえでの思いを明かします。

父と重ねて
蔦屋重三郎という役について勘九郎は、「最初はさまざまな困難に直面してうまくいかないこともあるのですが、皆の支えにより絵師や戯作者の新しい才能を発掘してプロデュースするという人物です。そこには“刷り物が好き”という熱い思いがあり、蔦屋のパワーの源だったのではないかと思います」と分析。「とてもパワフルで、頭のきれる名プロデューサーですので、父(勘三郎)と被る部分もありますね。父もさまざまな企画を立ち上げ、多くを成功させてきましたが、その根本には歌舞伎が大好きという思いがあるので、とても似ているなと思います」と、父・勘三郎と重ねながら、役について語りました。
続けて横内が、「みどころは、吉原大門の屋根の上で勘九郎さん演じる重三郎が叫ぶ場面です。お咎めを受け財産を持っていかれたあとに、持っていくなら全部持っていきやがれ、だけど絶対また新しいアーティストを見つけて育ててやるんだという啖呵を切る。独りよがりの叫びですが、ここの場面の勘三郎さんが凄かったんです。ただ、今回の勘九郎さんも負けていなくて、決して二人が向き合って闘っているわけではないのですが、私のなかで、お父さんと闘っている息子の姿に見えるんです。ここは37年前とあまり変えずほとんどそのままにしているので、ぜひご注目いただきたい」と、勘九郎の見せ場に触れます。
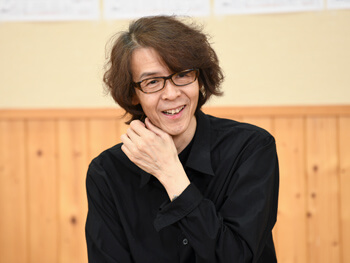
言葉と花魁
七之助は演じる遊女お篠について問われると、「家の理由があって売られてきた先で、若き日の重三郎に偶然出会います。もちろん重三郎の人間性もですが、彼が持ってくるキラキラとした生きている絵、そういうものに彼女は救われたんだと思います。寂しさのなかに楽しさや哀れさもあり、すべてが詰まっているように感じます。また今回はお篠が請け出されますので、その後の重三郎との関係も見ていただけたら」と、役の心境を丁寧に語ります。
重ねて横内が、「重三郎が刷り物として世に出したことで、それまで一部の人しか鑑賞できなかった絵や本を庶民が触れられるようになり、吉原では花魁に文字や楽器を覚えさせていたため、重三郎が出す本を遊女たちが読むことができた。お篠は“教養があり、言葉を知ってしまった花魁”で、廓の中にいても、心は自由だった新しい花魁なのかなと思います。僕は、言葉にはそういう力があると信じている」と分析し、勘九郎、七之助も強くうなずきました。
取材会の最後に勘九郎が、「あの役のこと言っちゃいけないの?」と発表されていない2役目について触れると、横内から「あれは勘三郎さんもすごかった!」と笑いながら話し、期待が膨らみます。
▼
歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」は25日(火)までの公演。チケットは、チケットWeb松竹、チケットホン松竹で販売中です。
