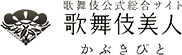歌舞伎文様考

『伊万里色絵花文六角腰瓦』(株)INAXライブミュージアム蔵
一枚のタイルの物語『志野釉菱重ね文(しのゆうひしかさねもん)敷瓦』
古くはエジプト、メソポタミアの建造物にもその存在が確認されている文様。人類が歩んで来た長い歴史の中で、文様はそれ自体が生命を持つがごとく、長く茎葉を伸ばし世界中に広がってきました。その文様の歴史に欠かせないのがタイルを中心とした陶板です。
今回はINAXのタイル博物館に所蔵されている貴重な作品の中から、『伊万里色絵花文六角腰瓦』をご紹介します。
伊万里と表される伊万里焼は、伊万里港から船で出荷された有田焼を含む肥前一帯の磁器の総称で、1610年(江戸時代)頃に朝鮮半島から来た陶工によって誕生したとされています。その種類は多様で、白地に青色の顔料(呉須)で下絵付けをした染付から始まり、1640年代に柿右衛門によって赤の顔料で上絵付けされた赤絵や、赤の他に緑、黄色、紫、青などの色絵具で上絵付けされた色絵が生まれました。
伊万里と言えば、色絵(赤絵)の創始者として知られる初代柿右衛門が庭先の柿の木の実を見つめながら困難を乗り越え、赤絵を完成させた有名な逸話はご存知の方も多いのではないでしょうか。ところがこの話は、大正元年(1912)十一代目片岡仁左衛門が歌舞伎で初演した「名工・柿右衛門」で始めて演じられたフィクションだそうです。ただし、初代柿右衛門が日本で始めて赤絵を完成させるためさまざまな苦悩と困難を乗り越えてきたことは事実で、この時の苦労は柿右衛門家に残る赤絵創業のいきさつを記した「覚」に書かれているそうです。
伊万里焼創始のころ盛んに作られた「染付」では、青顔料の成分であるコバルト(呉須)の発色は安定しており比較的容易に青色を得ることができました。対して酸化鉄の赤発色は非常に難しいことで知られています。
顔料の粒子の大きさや焼成条件が少しでも違うと同じ赤色を発色させることはできません。さらに顔料を調整し、美しい色が出る焼成の温度や時間といった条件を見つけ出すのも至難の業です。さらに赤色を鮮明に発色するために下地となる素地の白さも重要となります。
柿右衛門窯では、濁手(にごしで)と呼ばれる青みを極力取り去った特別に白い素地を用いることで明るい色調の色絵を得ています。今回紹介するタイルもまた、素地の白さがその上に描かれる色合いを決定付けています。鮮やかな赤を演出するために欠かせない余白の美を改めて感じさせてくれる一枚です。
文:愛知県常滑市INAXライブミュージアムものづくり工房 後藤泰男
歌舞伎文様考
バックナンバー
-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂
『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。
-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様
今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。
-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)
前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)
話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第10回 和事衣裳の文様と色彩
今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。
-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く
今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。
-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様
今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。
-

第7回 旅する「唐草模様」
数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。
-

第6回 役者紋を纏う
俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。
-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様
日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。
-

第4回 “演技する”文様
十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。
-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話
武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。
-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様
歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。
-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース
歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。