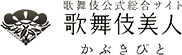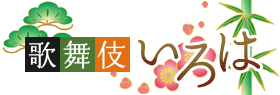
【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
 < < |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
長沼静きもの学院
-

新年から始める 新鮮でおしゃれな、きものの楽しみ
かしこまった場でのきものも素敵だけれど、もう少しきものを着るシーンを増やしたい…、そんなときにおすすめなのが、小紋や紬。帯や小物選びで着こなしの幅が広がる具体例をご紹介。
-

伝統から生み出される新しい美 きものをもっと楽しく、自由に!!
新たなきものの未来を拓く――。伝統の技を引継ぎながら、今の時代にふさわしいきものとは、と模索を続け、次々とアイディアを美しいきものにしている5人の現代作家のお話をうかがいました。
-

大切な”ひととき”をきもので――特別篇 トータルに美しくなる!
特別な日にふさわしいきものをプロが選んで着付け、きものに合ったヘアメイクを施し、記念の一枚を撮影。さらに、その日のために和の心を学び、中身からトータルで美しくなる...。そんな新スポットをご紹介。
バックナンバー
-

中村獅童×長沼静きもの学院 きもので歌舞伎を楽しむ!
恒例の長沼静きもの学院の歌舞伎セミナー。今回は、楽屋に入って化粧を始めると、その役に入っていくと言う獅童さんがゲスト。歌舞伎の化粧を実演しながらご紹介、化粧や衣裳の大切さをお話しています。
-

ここぞ!というときに最高のおしゃれ”キメル”きもの
結婚披露宴に華やかなパーティー、そして観劇。そのひとときを素晴らしい時間にしたいなら、迷わず「きもの」を選んでください。間違いのないおしゃれができる、それがきものなのです。
-

思ったより簡単!くみひもの楽しみ
玉に付けた絹の糸を交差しながら組む――。シンプルな動作だからこそ、無限の広がりを持つ工芸品、それがくみひも。始めたその日から、紐が組み上がる楽しさを実感できます。
-

新しい年、新しい自分発見!いつもの違うお正月きもの
お正月のおめかしきもの、何にしましょう? 年が改まるのをきかっけに、自分のイメージも変えてみませんか。いつもとちょっと違った自分発見、おすすめします。
-

きもので街へ!プチお出かけきもの
きものの楽しさを知るには、きものを着るのが一番! プロの着付できものの着心地を体感、そのまま街へ繰り出して、きものを着る楽しさをたっぷり味わってください。
-

夏こそきもので!超贅沢観劇スタイル
夏もきもので劇場へ。涼しげなきもの姿は、ほかの季節より断然、目立ちます。自信がない人はレンタル利用がおすすめ。プロの着付なら安心も倍増、夏も素敵なきものライフを!
-

きもので歌舞伎観劇!劇場が華やぐ装い
新しい歌舞伎座へきものでお出かけ、いかがでしょう。せっかくの晴れの舞台です。プロの手におまかせして、素敵なきもの姿をつくってみませんか。
-

大切な“ひととき”をきもので―5 娘の振袖を着付ける
娘の成人式に振袖を着付けたい...。そんな思いが、着付を学ぶ時間を生み出し、母娘の新たな絆を結ぶきっかけとなりました。
-

大切な“ひととき”をきもので―4 お正月だから、初めてのきもの
いざ、きもの!さて、何から始めればいいのか...。そんなときにレンタルきものはいかがでしょう。初めてでも安心、手軽にきものが楽しめます。
-

大切な“ひととき”をきもので―3 訪問着が一枚あれば
格調高く装うことも、華やかな席を彩ることもできるのが訪問着。いろいろなシチュエーションでもっともっと活躍させたい一枚です。
-

大切な“ひととき”をきもので―2 思い出に残る卒業式の袴姿
学生から社会人へ、旅立ちの"とき"を刻む袴姿。清楚ななかにも、心華やぐ気持ちをきものに込めて、一生の記念にふさわしい晴れ姿をつくります。
-

大切な“ひととき”をきもので―1 結婚式に着る留袖
大人の女性として恥ずかしくないきもの選び。あらたまった場だからこそ、自分の立場や思いが表れるそのきもの姿が、好印象となって残る着こなしを。
-

人生の節目に寄り添うきもの― 大切な“ひととき”はきもので
人生の様々な節目でめぐり会うのがきもの。ただ纏うだけでなく、そこに喜びや悲しみの気持ち、思いを込めることができる...。それがきものです。
-

歌舞伎美人読者特別企画 母娘で楽しむ夏のきもの
ご応募くださった母娘お二組が、夏物とゆかたの着こなしをご披露!ぴったりの一枚を素敵に見せてくださいました。
-

夏を先取り!更衣の季節です
6月は単衣(ひとえ)の季節。着るもので季節の移ろいを表すのが日本人の美意識。夏の訪れを楽しみましょう。
-

新緑に映えるきもの
色柄で季節を表現するきものの醍醐味が、存分に味わえるこの時節。さあ、とっておきのきもの姿で出かけましょう。
-

人生の節目を素敵に彩る――着付師という仕事
人生の節目となる日の特別なきもの姿を美しく形づくってくれる人、それが「着付師」。仕事の現場はさまざまで...
-

植物色を身にまとう――日本の「藍」
藍染のきものほど着る場所を選ばないものはない、ともいわれます。高度な職人技が生み出す「藍」の魅力に迫ります。
-

お正月を着る!――おめでたいきもの
普段はきものに親しむ機会の少ない人もきものが着たくなる時節。お正月ならではのきものの楽しみ、たっぷりご紹介します。
-

家族の”絆”を深める――心に残る「和婚」
家族を結ぶ"絆"に思いを新たにした今年、家族の絆、日本の絆を再認識させてくれた「和婚」に注目が集まりました。
-

これでわかった!残暑をのりきる「単衣」
9月にまとう単衣(ひとえ)のきものは、季節の移ろいを感じさせてくれます。たとえ残暑が厳しくても、気候に応じた単衣の楽しみ方を知っていれば安心です。
-

日本を着こなすゆかた
「ゆかた」には日本の伝統技術のすばらしさが息づいています。一枚さらりとまとうと、それだけで日本の夏を感じるゆかた。そんな魔法の魅力を持つゆかたの楽しみ方、着こなし方をご紹介。
-

日本の美をまとう――「結ぶ」
きものをはじめとする暮らしの様々を振り返ると、日本人がいかに「結ぶ」ことに長けていたかわかります。今回は夏きもので涼やかに「結び」、美しい着付のコツを教わります。
-

召しませ、きもの!初春のお出かけ着回し術
忘年会にクリスマス、家族で迎えるお正月から新年のご挨拶回りと、慌ただしいなかにも心浮き立つ季節がやってきました。きものを着たいという思いも高まるこの時期、年末年始のお出かけに、あなたならどんなきもので臨みたいですか?
-

きもので京都を歩きましょう
「きものを着て過ごせたら、もっと楽しいだろうな...」そんな思いに駆られる町、京都。その中心地に、きものレンタル・着付と、ヘアメイクが気軽にできる『長沼静きもの ひととき』がオープンしました。
-

夏こそ、きものを楽しもう!大人の女の夏きもの
憧れはあるけれど「夏きもの」は難しそう...というあなた。今年こそ「夏きもの」に挑戦してみませんか?盛夏に着る"うすもの"、初秋に着る"秋単衣"をご紹介します。
-

組紐が繋ぐ和の心、心の絆
きものを着る際、着付の最後に締める"帯締"。 この1本の紐には、知れば知るほど奥深い魅力が詰まっていました。
-

きもの美人のマナーレッスン
きものを着る際のマナーを知ることは、 日本人ならではの、きめ細やかな心配りといった "心"を知ることでもあります。
-

結婚式のきものルール
晴れの日をお祝いする結婚式の装い。今回は東京駅にある「長沼静 きものひととき」で レンタルできるきものからご紹介します。
-

きもので過ごす 東京の優雅な休日
東京駅で洋服からきものの装いにお色直し。女性のお洒落心を満たしてくれる素敵な場所を見つけました。
-

夏きもののいろは
手軽な浴衣も良いけれど、見る人の目にも涼しげな夏きものは大人の女性の憧れです。
-

涼やかな絹鳴りを求めて 〜博多織の工房を訪ねる〜
涼しげな夏のきものには、軽やかな夏帯をきりりと締めたいものです。夏帯の代表選手・博多帯の工房を訪れました。
-

主役は”愛着ある”小物
思いのこもった特別な小物は、装いに華やぎと気持ちのアクセントを与えてくれます。
-

春待月のきもの遊び
春待月(はるまちづき)とは12月の異名。冬だからこそ、あえて華やかな装いで春を待ってみませんか?
-

きもののお手入れ、収納方法を学ぶ
きもののお手入れ方法に自信はありますか?きものが傷みやすいこの季節、もう一度基本をおさらいしてみましょう。
-

涼を呼ぶ、夏の装い
夏の風物詩"ゆかた"。今年は落ち着いた大人のゆかたが注目です。
-

晴れの日の春きもの
軽やかな春の装いに、心も自然と華やぎます。
-

和の顔を学ぶ
きものに合わせて、メイクも髪型もひと工夫。きもの姿によりいっそうの輝きを与えてくれます。
-

冬を纏う幸せ
一年のうちで最もきものが恋しくなるのがこの季節。冬のきものを纏うだけで、晴れやかで優しい気持ちが生まれます。
-

美しき、秋の装い
秋の訪れとともに、きものも単衣から袷へと変わります。鑑賞の秋、行楽の秋、ときものを纏う機会は増えそうです
-

紬の島、奄美大島を訪ねて
美しい自然から生まれた天然染めの手織り、奄美大島紬。その魅力を知るべく、紬の島・奄美大島を訪ねました。
-

さらりと着こなす単衣のきもの
ほんのひとときの季節にだけ袖を通す特別なきもの「単衣」。季節のうつろいを肌で感じてみませんか。
-

きらりと光る和のお作法
今回は、より美しい立ち居振る舞いをできるよう、基本的なきもののお作法をおさらいしましょう。
-

夏の遊び着・ゆかたを楽しむ
夏の風物詩のひとつ、ゆかたの装い。一足先にワンランク上の大人のゆかた姿を楽しんでみませんか。
-

帯結びのいろは
一本の帯が作り上げる世界は無限大。きもの・帯・そして着る人に合わせて、創作のイマジネーションは広がります。
-

組紐の里、伊賀を訪ねて
きものの帯締めとして使用される組紐。産地として有名なのは、東京、京都、そして伊賀の名が挙げられます。