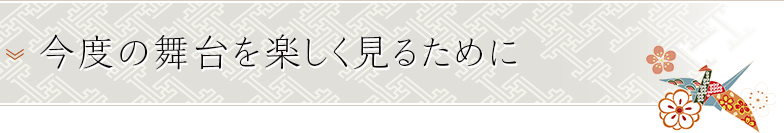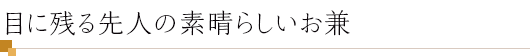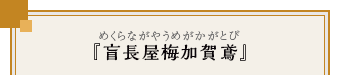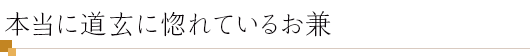【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
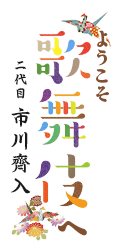

――『加賀鳶』のお兼が、二代目市川齊入襲名披露のお役になります。初役ですが、どんな役づくりをなさろうとお思いですか。
六代目菊五郎さんの道玄からお兼をお勤めになり、当り役にされた(三世尾上)多賀之丞さんの舞台が目に残っております。楽屋での雰囲気そのままに、舞台に出られてお兼になっていらっしゃいました。なかなかああはできないと思います。(二世尾上)松緑さんの道玄となさった(四世中村)雀右衛門のおじさんのお兼も、色気があって素晴らしかったです(昭和56年10月歌舞伎座)。
――海老蔵さんが勤められる道玄の愛人ですね。
『義賢最期』で奥方の葵御前(海老蔵の義賢)、『夏祭』で女房のお梶(海老蔵の団七)を勤めさせていただいたこともございます。実年齢なら、お母さん役でしょう。相応しいように若返って演じるつもりです。とてもうれしいです。
大名火消の加賀鳶が本郷通りに勢揃い、松蔵親分も一緒になって定火消に喧嘩を仕掛けようというところ、頭の梅吉が留め立てします。所変わってお茶の水の土手には、療治と見せかけ懐の金を盗んだ挙句、百姓を殺した按摩の道玄。落とした莨入れを拾ったのは松蔵でした。
一方、道玄の家では女房のおせつに、姪のお朝が金を持ってきました。難儀をする叔母にと奉公先の伊勢屋の旦那がくれたと言うお朝に、嘘をつくなと道玄が問い詰め、同居しているお兼も加わります。お朝を人買いに渡し、二人は強請りの算段を始めました。そして、伊勢屋の店先に居座り、お朝を疵物にしたと強請る道玄とお兼。しかし、松蔵親分に追い詰められ、すごすごと帰ってきました。
面白くない道玄が家でお兼と酒を酌み交わしていると、大家が道玄のものではないかと血の付いた着物を持ってきました。身に覚えのある道玄は慌てて大家を追い帰し、本郷の赤門までは逃げてきましたが、悪運尽き、とうとうお縄にかかってしまいました。
――お兼は道玄と二人、「質見世」で主人の与兵衛を強請り(ゆすり)に出かけます。このとき、「二朱より安い療治はしないよ」というせりふがあります。かなりきわどい生き方をしてきた女性ですね。
嫌らしい感じがあったほうがいいと思います。この人のなかにはドロドロした部分があります。きっと怪しいことをたくさんして生きてきたんだろうと思います。自分自身のなかにある嫌らしさを出さなければならないということですね。
お朝を責めるところでも、口がうまいんですよ。字は読めなくても頭はよく、悪知恵が働きます。女房のおせつを折檻する道玄に向かい、「本当にひどい人だね」なんて言いながらも笑っています。道玄のことを本当に好きで、道玄もお兼を嫌いではないはずです。
――黙阿弥のせりふも耳に心地いい作品です。
黙阿弥さんは気持ちよく、せりふは言いやすいのですが、テンポに乗っているだけでは、気持ちがおろそかになってしまいます。するするっと通過していっては、いけないと思います。私は生まれが大阪なものですから、江戸弁があまりうまくないので、しっかり勉強して勤めようと思います。
――どんなところを大切に演じられますか。
雰囲気ですね。亡くなった(十二世市川)團十郎の旦那は、「それらしく見えればいいんだよ」とおっしゃっていました。人物そのものになれるわけはありません。それらしく見せるのが我々の仕事です。役のなかに自分が出てくればいいのかなと思います。
いろいろつくるよりも、ぱっと出たほうが自然にできることもあるのでは、とも思います。江戸の底辺に、こういう人たちがいたんだろうなとお客様に思っていただけるように演じたいです。
ようこそ歌舞伎へ
-

『熊谷陣屋』中村吉右衛門
花道の出から幕外の引込みまで通す熊谷の性根、それが、どれだけお客様に伝わるか――。「熊谷が泣かずにお客様が泣いてくだされば最高です」という吉右衛門さん、演じるたびに工夫を重ね、今回も特に考えている箇所があるといいます。心情をせりふだけでなく、形でも表すのが歌舞伎。美しい形ひとつからも熊谷の心がうかがえます。一瞬も聞き逃さず、見逃さずご堪能ください。
-

『寿曽我対面』尾上松也
「新春浅草歌舞伎」で2度目の五郎を演じる松也さん。6年前の初役は荒事の経験がほとんどないなか、文字どおりの挑戦でしたが、芯となる立役も数多く経験してきた今は、次の課題もしっかり見据えています。「純粋でまっすぐで、血気盛ん」な五郎を勢いで見せるのではなく、「一つひとつの形を絵のように」きめるのは至難の業。これまでの浅草での経験と自信が、お正月らしいこのひと幕に凝縮します。
-

『義経千本桜』「木の実」「すし屋」片岡仁左衛門
「木の実」でのさりげないやりとりが「すし屋」で生きてきて、権太の悲劇が際立つ――。お客様には権太の心情に心を寄せ、ドラマに入り込んで芝居を見てほしいからと、仁左衛門さんはさまざまな工夫を凝らして権太を勤めます。悪事を働いても憎めない、愛嬌があって可愛いなと思わせる仁左衛門さんの権太が、南座に登場するのはなんと初めて。新開場にふさわしい、見逃せない権太になります。
バックナンバー
-

『雁のたより』中村鴈治郎
新しくなった南座で、3年ぶりの顔見世興行。そこで上演されるのが、上方の匂いあふれる『雁のたより』です。「型があるようで、ない」髪結の三二五郎七、周りとのやりとりが芝居の鍵で、その日その日の雰囲気できまる部分もあるのだとか。髪結床には鴈治郎さんのイ菱の紋があしらわれ、小道具にもイ菱、そして黒御簾音楽まで、鴈治郎づくしの芝居のはじまりはじまり
-

『与話情浮名横櫛』中村梅玉
しがねえ恋の情けが仇――。誰もが知るこの名ぜりふは、自分もある程度酔って言うことが大事、でも、上滑りするようではだめで、その日のお客様の雰囲気に合わせることも必要とのこと。名場面の裏にはやはり、舞台の積み重ねがありました。手順や型の多い芝居だけに、最初は大変だったと明かした梅玉さん。「見染」のあの羽織落としのこと、「源氏店」の34カ所の傷についてもうかがっています。
-

『俊寛』中村歌六
理屈っぽくならずに颯爽と登場することで、お客様を納得させる丹左衛門尉基康。正論を言っている赤っ面の瀬尾との対比を、見た目にもくっきり出しています。祖父、三世時蔵も演じた役で、先祖がやった役というのはやはりうれしいもの、と歌六さん。初代吉右衛門を顕彰する「秀山祭」で今年は2演目に出演、その初代との微笑ましいエピソードも明かしてもらいました。
-

『盟三五大切』中村七之助
「小万は面白い人だと思います」。自分に入れ上げた源五兵衛から、ひと芝居打って金を巻き上げ、好きな男に渡してしまう小万ですが、そこに純粋な心を見る七之助さんは、悪い人と思われないようにしたいと語ります。コクーン歌舞伎で上演されたときの思い出、さらには納涼歌舞伎に向けての決意が、初役の小万役を特別な挑戦にしているようです。
-

『人情噺文七元結』中村芝翫
これは喜劇ではなく、人情噺。そのひと言の教えを大切に、せりふひとつ、動きひとつ、おろそかにすることなく長兵衛を演じる芝翫さん。「人間性が見え隠れするのが、世話物の立役の大事なところ」と言い、自分が芝居をするところではなく、他人の話を聞くようなところも、やっぱり長兵衛さん。だからこそ、この人情噺が息づき、人の心を動かし、温かい気持ちにさせてくれるのだと気づきます。
-

『妹背山婦女庭訓』「三笠山御殿」中村時蔵
初舞台も、五代目襲名もこの「三笠山御殿」でした。時蔵さんにとっては、祖父、父の追善に演じるほど思いの詰まったお三輪、「成駒屋のおじさん(六世中村歌右衛門)の教え」が、一瞬一瞬に詰まっています。馬子唄、独吟、疑着の相…、見せどころは満載ですが、「お三輪の心にはいつも、求女さん」、その一途な心がいつの時代も客席の心を打ちます。
-

『弁天娘女男白浪』尾上菊五郎
娘に化けて登場した弁天小僧が、「稲瀬川勢揃」では、格好よくきめて名のりを上げる…。「立役がよくなると女方が気になるし、女方を一所懸命にやると立役が気になる」。菊五郎さんが数えきれないほど演じた弁天小僧の難しさは、観るほうにとっての面白さにほかなりません。舞台上の全員が絶妙のバランスでつくり上げるこの演目の秘密に迫ります。
-

『絵本合法衢』片岡仁左衛門
「普段できないことができる面白さがあります」と、悪人を演じる魅力を語った仁左衛門さん。役をつかまえれば、自然とその人物になれる、そのためには台本を読み直すことが大切で、読み返すたびに発見があるそうです。何度観ても新鮮な感動を呼び起こす舞台について、そして、大学之助、太平次の2役に別れを告げることへの思いを聞きました。
-

『於染久松色読販』坂東玉三郎
お染の七役の早替りで知られる『於染久松色読販』ですが、今回は、土手のお六が活躍する強請場(ゆすりば)を抜き出し、芝居の面白さをたっぷり見せます。教えられたとおりに勤めた初演から、回を重ね、ほかの南北作品や泉鏡花、丸本物を勤めるうちに、「南北のせりふはこういうものとわかってきた」と語ります。
-

『一條大蔵譚』十代目松本幸四郎
長成のせりふにはあらゆる音が必要とされ、語る言葉一つひとつが重い、という幸四郎さん。愛嬌と品がなければ成立しないつくり阿呆には、型どおりに動きながら阿呆に見せる難しさもあります。「このお芝居ができる役者になるのが目標でした」と、計り知れない思いを胸に、2カ月目の襲名披露の舞台に立ちます。
-

『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」二代目松本白鸚
高麗屋三代が37年ぶりに襲名披露する舞台で、二代目白鸚さんが演じるのが『寺子屋』の松王丸。「考え抜かれたせりふが随所にあります」と言い、せりふ一つ、咳一つ、細やかな心理描写がドラマに厚みをつけます。考え抜かれた松王丸、一瞬たりとも目の離せない舞台で、今、白鸚という新たな道へと踏み出します。
-

『蘭平物狂』尾上松緑
物狂いの踊りは説得力を持たせ、正体を明かしてからは凛々しい姿をお見せし、後半は数ある演目の中でも屈指の立廻りを披露する『蘭平物狂』。「一人でできる芝居ではありません」と松緑さんが語るこの演目、今回は、息子の左近さんや次世代に向けて「自分の集大成となる蘭平を」と、特別な気持ちで臨みます。
-

『奥州安達原』中村吉右衛門
「こんな演出、よく考えたものだと思います」。正体を見破られた貞任が見せるケレン的な演出に、先人への尊敬を込め、袖萩とお君の母子の描き方に、作劇のうまさを見る吉右衛門さん。その根底にあるものとは…。11年ぶりの貞任役にかける思い、さらに、歌舞伎について、好きな役についてもうかがいました。
-

『蜘蛛絲梓弦』『春重四海波』片岡愛之助
五変化舞踊と新喜劇を元にした芝居、まったく異なる2演目ですが、実は「衣裳を替えるのが大変」という共通項が。『蜘蛛絲梓弦』の早替りもさることながら、幕ごとにがらりと年齢の異なる役で登場する『春重四海波』の拵えも大忙しとのこと。どちらも今回が待望の再演、磨き上げて前回とはまた違った舞台を披露します。
-

『極付幡随長兵衛』「ひらかな盛衰記」中村歌六
「秀山祭で秀山様がなさったお役をさせていただくのがうれしい」と、2度目の権四郎を演じる『ひらかな盛衰記』「逆櫓」。同じく2度目となる唐犬権兵衛が格好よくきめるのは、「完全なる男の世界」を描く『極付幡随長兵衛』。歌六さんが見せるのは、年齢も違えば身分も異なる2役ですが、どちらも一本筋の通った男。俠気を見せます。
-

『刺青寄偶』中村七之助
芝居の前半と後半でがらりと様子の変わるお仲を初役で勤める七之助さん、どう変えたらいいかなんて考える必要はない、「ただ半太郎さんを愛せばいいんです」ときっぱり。刺青を彫るお仲の気持ちも語ってくれました。最後の半太郎の大勝負、この後の描かれていない二人の行方をも想像させる芝居にと意気込みを見せます。
-

『盲長屋梅加賀鳶』市川齊入
『加賀鳶』ではいろいろな役を勤めてきましたが、お兼は初役。「この人のなかにはドロドロした部分がある」という齊入さん。本名は曾祖父の初代齊入から1字を取って付けられたそうで、今回の二代目襲名にも「ご縁を感じます」。六世歌右衛門、十二世團十郎からの言葉を胸に刻み、襲名披露の舞台に立ちます。
-

『曽我綉俠御所染』市川左團次
初演のときに十七世羽左衛門さんから教わったことからはみ出さず、きちっと受け取って勤めているという左團次さん。幕開きの五郎蔵や子分たちとの応酬は、この芝居の醍醐味の一つですが、やはり渡りぜりふは緊張するそう。たくさんの先輩俳優から受けた教えを、ありがたいことと振り返ります。
-

『梶原平三誉石切』『曽我対面』九代目坂東彦三郎
祖父、父と同じく襲名で十五代目羽左衛門型を見せる梶原。居並ぶ先輩俳優の「胸を借りるつもりで」勤める五郎。最近、似ているといわれることも多くなったという祖父、十七世羽左衛門さんからは、「子ども扱いされなかった」くらい、厳しい教えを受けたそう。その教えが舞台で今、花を咲かせます。
-

『夢幻恋双紙~赤目の転生~』中村勘九郎
一つひとつのせりふに込められた意味を探り、それがお客様にしっかり伝わるようにと、稽古に集中する勘九郎さん。「何度ご覧いただいても、新たな発見がある作品です」。ひと言も聞き逃せない、一瞬も見逃せない舞台が始まります。
-

『助六由縁江戸桜』中村雀右衛門
雀右衛門襲名から1年余、数々の大役を勤めてきましたが、揚巻は「死ぬまでにさせていただけるような幸運な機会があれば」と思っていた念願の役。父、四世雀右衛門の揚巻を白玉として同じ舞台で見てきた雀右衛門さん、「父になぞってさせていただく」と意気込みを見せました。
-

祇園祭礼信仰記『金閣寺』中村歌昇
若手中心の花形歌舞伎で、古典中の古典の大役に挑戦する歌昇さん。「何が難しいというのが、わからないくらい難しい」と言いつつも、少しでも高みに近づこうと努力を続けています。秀吉がモデルといっても、キャラクターは歴史上の人物とは異なり、芝居の前半と後半でも違ってきます。細かく書き込みの入った台本を手に、今日も全力でぶつかります。
-

『雙生隅田川』三代目市川右團次
右團次家の芸、「鯉つかみ」を大詰で演じるところで、劇中口上が入る今回の演出。「これまで育てていただいた」澤瀉屋の師匠、猿翁が大切にしてきたケレン味がたっぷり入った『雙生隅田川』での右團次襲名です。たくさんの思い、縁、歴史が詰め込まれた舞台に立つ三代目、息子の二代目市川右近の初舞台も楽しみです。
-

『あらしのよるに』中村獅童
絵本から歌舞伎へ――。歌舞伎の持つ表現方法にこだわってつくり上げた『あらしのよるに』が、歌舞伎座登場。「せりふが増え、がぶとめいの芝居も増えます」と、獅童さん。お客様に受け入れてもらえるのかという初演のどきどきから、もっと楽しんでいただきたいと変化を見せるこの再演、見逃すことはできません。
-

歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」『祝勢揃壽連獅子』『加賀鳶』『芝翫奴』四代目中村橋之助 三代目中村福之助 四代目中村歌之助
歌舞伎座での襲名披露興行も2カ月目、新しい名前で気持ちも新たに舞台に臨む三人が語ります。親子四人での『連獅子』へ向ける特別な思い、同じ鳶でもそれぞれ心に期するところが異なる『加賀鳶』、そして、歌舞伎座の大きな舞台に一人立つ『芝翫奴』に向けての稽古…。兄弟三人の個性が見えてきました。
-

『熊谷陣屋』八代目中村芝翫
歌舞伎座で2カ月の襲名披露興行を行う芝翫さん。芝翫として八代目にして歌舞伎座で初めて芝翫型の『熊谷陣屋』を見せます。熊谷と相模、夫婦の思いがより印象深く見えるのが芝翫型。團十郎型とは衣裳や演技が異なるので、また違った味わいが生まれることでしょう。襲名への熱い思いを大先輩の思い出とともに語ります。
-

『太刀盗人』中村又五郎
隣で踊る田舎者を見よう見まねで踊るため、少しずつ踊りがずれる。…といっても、ずれてしまうのではなく、ずれる振りを「きっちりお見せすることが大切」と又五郎さん。踊り手は大変ですが、一所懸命さを見せるのではなく、ほんわか、楽しいものにしたいとも。そのためには身体に“ずる”をさせないこと、だそうです。
-

『権三と助十』坂東彌十郎
「最近、家主を演じる機会が増えました」と、にっこり笑顔で語り始めた彌十郎さん。しかし、この作品の家主、六郎兵衛はちょっとこれまでとは違うと表情を引き締め、初役への意気込みを見せました。父、好太郎さんの舞台姿が目に残るという六郎兵衛、そして、大好きな「納涼歌舞伎」についてもたっぷり語ります。
-

『鳴神』中村梅枝
お姫様の情熱的な部分もあり、色気も大事、知的で、品も格もなくてはいけないしと、女方のさまざまな要素が一つになった屈指の大役に初挑戦。最近はつくづく自分が女方だなと実感しているそうで、体力的にもきついといわれる雲の絶間姫ですが、夏の公演に向け、意気込みは十分です。
-

『義経千本桜』市川染五郎
子どもの頃から憧れていた知盛に初挑戦。義経を討たんとの一心で生きる、その思いの深さを役に込めます。がらっと変わって第二部では柔らか味や華やかさを出す弥助、そして第三部では狐忠信ではなく静御前で踊ります。『義経千本桜』という作品のなかでそれぞれの役がどういう存在であるのか、明確に描き出します。
-

『十六夜清心』『三人吉三巴白浪』尾上菊之助
5演目で5役を勤め、長男の和史さんの初お目見得もある今年の團菊祭。初役で挑む『十六夜清心』の清心、同じ女装した盗賊でも弁天小僧より色気が必要だと言うお嬢吉三、2本の黙阿弥作品に出演する菊之助さんは、その難しさをせりふの意味と心地よいリズムのバランスだと語っています。
-

『彦山権誓助剱』中村東蔵
性根の強い役が多いのが、義太夫物の老婆、お幸も「並のお婆さんではありません」と東蔵さん。経験を重ねてきて、この役はこう、というこだわりから離れてきたそうです。その役にさえなれば、その役に見えれば何でもあり、と役をつくる楽しさが舞台にも表れます。
-

『鎌倉三代記』『祇園祭礼信仰記』五代目中村雀右衛門
情を大事に、そして姫であり続けること――。『鎌倉三代記』時姫は初役、『祇園祭礼信仰記』雪姫は2度目、襲名披露狂言は華やかな赤姫2役です。「三姫に共通するのは思いの強さ」と、五代目雀右衛門の名を得て気持ちも新たに挑む舞台、その華やかな姫に期待が高まります。
-

『新書太閤記』尾上菊五郎
原作の魅力に「お芝居風の決着」をつけ、「面白く、わかりやすく、明るい楽しい感じに」つくりたいと意気込む菊五郎さん。六世菊五郎から当代へ生まれ変わった『新書太閤記』、出演者もそろって豪華な舞台になりそうです。
-

『桂川連理柵』「帯屋」中村壱太郎
お客様が入らないとわからない芝居――。祖父の藤十郎さんからのひと言が身に染みたという初演から、早くも2度目の長吉、お半に挑む壱太郎さん。一途な恋に身を焦がす14歳の娘と口の立つ上方の丁稚、興味津々の2役です。
-

『碁盤太平記』中村扇雀
南座の2階には初世鴈治郎のブロンズ像。今回はその視線をより強く感じるのではと言う扇雀さん。「玩辞楼十二曲」でも上演の少ない演目に取り組み、いつかは全部を手がけたいと意気込みます。
-

『若き日の信長』『河内山』市川海老蔵
憧れの人、十一世團十郎を偲ぶ公演で、その十一世の当り役に挑む海老蔵さん。「初演や再演のときの自分に負ける気がしない」と言う信長と、「プレッシャーをかけて」初挑戦する河内山。さらに、長男、勸玄君の初お目見得も楽しみな公演です。
-

『あんまと泥棒』『松浦の太鼓』中村歌六
演技の引き出しをフルに開けて、と歌六さん。二人芝居の『あんまと泥棒』が新歌舞伎のレパートリーとなるようにと初役に挑戦します。二人芝居も『松浦の太鼓』の其角も、会話のキャッチボールが大切だそうです。
-

『お染の七役』中村七之助
「七之助が七役やっているな」で終わらないよう、個々のキャラクターをしっかり演じること――。それぞれの役を演じたことで、挑戦したくなった役もあると言います。再演の舞台、そして「赤坂大歌舞伎」への思いを語ります。
-

『新・水滸伝』市川右近
三代猿之助の薫陶を受けた面々が集まる二十一世紀歌舞伎組。師から学んだことを創作の場に注ぎ込み、再演のたびに工夫を重ねてきました。今回もお客様のためにと、新たな演出が加えられ...。
-

『御存鈴ヶ森』中村錦之助
これまでは権八ばかり見ていたと言う錦之助さんですが、自他ともに認める大親分、長兵衛をいかに演じるか、せりふの一つひとつに磨きをかけ、わずかな動きにも心を配って意欲的に挑戦します。
-

『播州皿屋敷』中村梅玉
『番町皿屋敷』の青山播磨は何度も勤めている梅玉さんですが、こちらの皿屋敷の浅山鉄山はなんと初役。「敵役のほうが似合っていますね、と言われるところまでいきたい」と、意欲満々です。
-

『男の花道』市川猿之助
工夫に工夫を重ねてつくり上げられた芸も、上演の機会がないと消えてしまいます。秘伝口伝を次の世代に受け渡すつもりで、どうしたらお客様に楽しんでいただけるかに心を砕き、役を勤めます。
-

『芦屋道満大内鑑』中村時蔵
筆を口にくわえての曲書きや早替り、ケレンの部分はしっかりやったうえで、親子の情を大事に勤めたい、と時蔵さん。金丸座の装置を使い、小屋の雰囲気を活かしてやるのが面白いと言います。
-

『菅原伝授手習鑑』尾上菊之助
今回の上演で桜丸を通して演じる菊之助さん。役柄の性根は通っていても、「加茂堤」「車引」「賀の祝」、それぞれの場面で表現方法が異なると言います。
-

『傾域反魂香』『連獅子』四代目中村鴈治郎
2カ月連続の大阪での四代目鴈治郎襲名披露。お正月とは"色を変え"、また、いつもとは違うやり方でお見せする襲名披露狂言。襲名だからこその気持ちが込められた舞台、見逃すわけにはいきません。
-

『新口村』片岡秀太郎
人に教えているうちに自分でもやりたくなって…、大好きな梅川で顔見世に登場する秀太郎さん。「かわいい、愛おしい、抱きしめたくなるような梅川」は、毎日の工夫の積み重ねから生まれます。
-

『熊谷陣屋』松本幸四郎
「直実は坂東武者だからね」と、父の初世白鸚さんは稽古の折に幾度となく口にしていたそうです。幸四郎さんは、戦争の世に生きる熊谷と相模の夫婦愛に焦点を当ててこの一幕を演じます。
-

『伊勢音頭恋寝刃』中村勘九郎
"ぴんとこな"に分類される貢の役は、受けの芝居が多くてきついところもあり、「すごく難しい役です」と勘九郎さん。前回は悩み苦しんだと言う貢に再挑戦、柔らかさを大切に演じます。
-

『法界坊』「絵本太功記」中村吉右衛門
何より伝えたいのは、伝統歌舞伎というものの"型"、"演出"――。初代ゆかりの芸の伝承をはかる「秀山祭」、これだけすごい俳優がいたんだと知っていただくため、吉右衛門さんがゆかりの2役を勤めます。
-

『信州川中島合戦』「輝虎配膳」中村橋之助
「ただの短気な血の気の多い人間ではありません」。十三世仁左衛門さんの教えを守って芯の強い武将にしたいと、念願かなっての初役、輝虎にさまざまな思いを込めて舞台に立ちます。
-

『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」片岡仁左衛門
初演では首実検で思わず涙が出てしまったという仁左衛門さん。再演を重ねている松王丸は、父、十三世仁左衛門さんからの教えがたっぷり詰まったお役です。その松王丸で1年ぶりに大阪の舞台に立ちます。
-

『三人吉三』尾上松也
演出家に感想を聞かれることもあれば、自分の考えが演出家に取り入れられることもある――。初めてのコクーン歌舞伎の稽古場でやりがいを感じながら、初役のお坊吉三をつくり上げていきます。
-

『伊達の十役』市川染五郎
この芝居の政岡を演じるために、これまで女方を手掛けてきたと、胸に秘めていた熱い思いを語った染五郎さん。高麗屋ゆかりの仁木弾正も登場する全十役、すべて「猿翁のおじ様の演出どおりにいたします」。
-

『鎌倉三代記』中村魁春
八重垣姫も雪姫も勤めた魁春さんが、「三姫」で最も難しいと言う時姫。「いい形をしようと思ったら、もうダメです」。あくまでもお姫様の心で動かなければ、代々が磨き上げてきた形にならないそうです。
-

『素襖落』尾上松緑
ほろ酔い加減で踊っているうちに酔いが回り、足元がおぼつかなくなるさまを、手順ではなく体に叩き込んで自然に見せる――。きっちり踊り、風情も醸し出す、難しい狂言舞踊に挑戦します。
-

『封印切』中村翫雀
2階から駆け降りたり、封印を切ったり、しどころの多い役ですが、難しいのは「梅川と、ただじゃらじゃら、うだうだしているだけ」のところだとか。相手とのやりとりに上方歌舞伎の味がにじみ出ます。
-

『仮名手本忠臣蔵』「九段目」坂田藤十郎
「たぶん、戸無瀬よりお石のほうが年上でしょう。戸無瀬は若さが残っていないといけない」。せりふの間の取り方、演技で若さを表現する藤十郎さん。大顔合わせの舞台、期待がふくらみます。
-

『ぢいさんばあさん』市川中車
「第一幕と二幕は甘く気障に。それが澤瀉屋の伊織」と、父の猿翁さんに言われた中車さん。そして第三幕は...。京の顔見世で演じる2役のほか、息子の團子さんについてもたっぷり語っていただきました。
-

『瞼の母』中村獅童
リアルにさらさらとやるのも、歌い上げすぎるのもよくない。気持ちを込めて、しかもリアルに演じる難しさ。でも、その心底には亡き勘三郎さんからもらったうれしいひと言があります。
-

『義経千本桜』中村梅玉
父、六代目歌右衛門との共演によって生まれた素敵な"瞬間"とは? 源平の世界の代表的人物、義経を、梅玉さんが「テクニックよりも性根を大事に」演じます。
-

『男女道成寺』片岡孝太郎
これまで3回演じている白拍子花子。相手役の左近を演じる俳優さんに合わせる大変さもありますが、女方として上手の高いところで最後にきまるのは、やはり気持ちのよいものだそう。
-

『狐狸狐狸ばなし』中村扇雀
思い出の多い納涼歌舞伎で、初役に挑戦する扇雀さん。衣裳から演技までいろんな工夫と、毎日の積み重ねで、舞台の本番が始まってもきっと芝居が変化していくだろうとのこと。楽しみです。
-

『東海道四谷怪談』尾上菊之助
南北は「沼地に生温かい風が吹くような、どろっとした感じがする」と言う菊之助さん。六世梅幸の型をきっちり受継ぎながら、役の性根をつかんで面白さを発見しようと意欲的に挑みます。
-

『六歌仙容彩 喜撰』坂東三津五郎
「いい曲だなと思いながら踊っている瞬間が増えてきましたね」と三津五郎さん。三津五郎家が代々大切にしてきた『喜撰』は、第四期歌舞伎座の柿葺落でも上演された演目です。
-

『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」松本幸四郎
我が子の首を差し出す忠義と、親子の情愛――。現代のお客様が見て感動してもらえるようにと、せりふの一音、動き一つにこだわって松王丸を勤める幸四郎さん。これからの歌舞伎にかける思いが伝わります。
-

『籌祝歌舞伎華彩』坂田藤十郎
「こういう時期に居合せるのは俳優として幸運」との喜びを、舞台に立つ者の責任として受け止め、新しい劇場への一歩を踏み出す藤十郎さん。記念すべき一幕を華やかに開けます。
-

『暗闇の丑松』尾上松緑
序幕でくっきり丑松像を描き出す...。父のイメージを大事に演じたいと言う松緑さんが初役で挑戦。よく書きこまれた登場人物たちとのアンサンブルもみどころです。
-

『新八犬伝』『GOEMON』片岡愛之助
平成若衆歌舞伎、そしてシスティーナ歌舞伎として上演した作品を、ホームグラウンドの大阪で再演できることがうれしいと、愛之助さん。大奮闘です!
-

『仮名手本忠臣蔵』中村芝雀
遊女だったり、女房だったり、かわいい妹だったり。自分の気持ちを押し出し、舞台でいろんなことができる、それがお軽。そのやりがいのある役に挑みます。
-

『仮名手本忠臣蔵』片岡仁左衛門
「古典物についてはあまり掘り下げすぎてもいけません。現代風になりかねない」という仁左衛門さんが見せる、父、十三代目仁左衛門型の勘平。
-

『傾域反魂香』市川右近
見て聞いて"感じ"を取る...。澤瀉屋の教えどおり、初世猿翁さんの音声と、同じ舞台に立ったときの師匠、猿翁さんの"感じ"から又平をつくり上げます。
-

『八重桐噺』中村時蔵
八重桐は今回が4回目。内面的な要素を踊りに頼らず、芝居として表現するのが、萬屋さんの"しゃべり"。最後はぶっ返り、立廻りで華やかに魅せます!
-

『妹背山婦女庭訓』「三笠山御殿」中村七之助
最近、演じた役を通じ、あらためて古典作品の大切さに気づいたという七之助さんが、初役で挑むお三輪。苧環の扱いにはちょっと自信があるそうです。
-

新橋演舞場『桜姫東文章』中村福助
転落していくお姫様――。だからこそ「品位を大切に」演じるという福助さん。大好きな"南北の描く女性"とは、いったいどんな女性?
-

大阪松竹座『吉野山』三代目 中村又五郎
「私はわりと熱血居士で...」一所懸命踊ってしまうことがマイナスになることもあるという難しさ。又五郎さんが心を砕いているポイントとは?
-

新橋演舞場『ヤマトタケル』四代目 市川猿之助
「寂しさの強いヤマトタケルになるだろう」...果たして、新 猿之助さんの初演は作品の原作者、梅原猛氏の言葉どおりとなるのでしょうか。
-

大阪松竹座『絵本太功記』市川團十郎
なんといっても難しいのは"大落とし"――。團十郎さんが再演を重ねてたどり着いた光秀の見せどころほか、舞台鑑賞が楽しみになるお話をたっぷりと。
-

平成中村座『小笠原騒動』中村橋之助
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。岡田良助役にかける橋之助さんの熱い思い、そして、あの水車小屋の立廻りが生まれたきっかけについても語っていただきました。
-

京都四條南座『平家女護島 俊寛』中村吉右衛門
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。初代が得意とした俊寛僧都を、当代吉右衛門さんがどう演じられるのか、俊寛の心の移り変わりを追いながらお話しいただきました。
-

新橋演舞場『春興鏡獅子』六代目 中村勘九郎
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。祖父の芝翫さん、父の勘三郎さんから受け継いだ大切な役で襲名する新 勘九郎さん、その熱い思いを聞いてください
-

大阪松竹座『雷神不動北山櫻』市川海老蔵
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。歌舞伎十八番の演目が三つも入った通し狂言、海老蔵さんが勤める5役に込める熱い思いをたっぷり語ります。
-

日生劇場『碁盤忠信』市川染五郎
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。百年前に曾祖父が襲名披露で演じた役を染五郎さんがつくり上げます。そのチャレンジの決意やいかに!
-

新橋演舞場『髪結新三』尾上菊五郎
出演演目を歌舞伎俳優がご紹介。作品の魅力、演じる役の魅力、そして俳優の魅力。観劇前に一読すれば、舞台の面白さも倍増です。