歌舞伎文様考

役者の存在感を際立たせる大道具
長谷川勘兵衛さんは歌舞伎大道具の祖と言われる初代の名を受け継ぐ大道具師です。初代は日本橋宮大工の息子で、六代目は享保年間(1716〜1735年)に歌舞伎の大道具開発に全力を注ぎ、江戸三座の全ての大道具を受け持つようになりました。
今回も前回に引き続き、貴重な道具帳を拝見しながらお話を伺います。
歌舞伎の大道具に描かれる文様は、出演する俳優と話し合いを重ねながら制作されます。「道具は役者を引き立たせるもの」とおっしゃる大道具方の意匠は、細かなところにも施されています。
長谷川「例えば『籠釣瓶花街酔醒』の「縁切り」の場で、下手の後ろに花魁八ツ橋に贈られた積夜具(つみやぐ)(※1)が収納された棚が描かれていますよね。これは成駒屋さんが出演した時に作った道具帳なので、布団にかけた油箪(ゆたん)(※2)に「祇園守」の紋を描いています」
伊藤「道具の中に役者紋を描くだけで、舞台に立つ俳優の存在が空間に広がる印象を受けますね」
長谷川「例えば花魁が登場する芝居でも、自分の部屋を持てない花魁の部屋を描く時はこういった布団はないわけです。この場面では、贔屓から夜具一式を贈られる格の高い花魁の部屋に俳優の紋を入れることで、主役を勤める俳優の華々しさが増す効果があるんです」
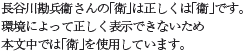

色鮮やかな道具帳を前に対談する十七代目長谷川勘兵衛さん(左)と伊藤俊治さん
つみやぐ(※1)
遊郭で、馴染み客から遊女に贈られた新調の夜具を積んで飾ったもの
ゆたん(※2)
油紙・木綿などでつくられた、箪笥・長持ち等を汚れから守る、道具の覆いのこと
歌舞伎俳優にはそれぞれの家を表わす家紋の他、花紋もあります。大道具をよく見るとその意匠がそこここに施されていると言います。
長谷川「『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』では、赤い大格子の下に“腰”と呼ばれる板があります。ここには唐草が描かれるのですが、市川團十郎をはじめ、成田屋の一門が助六を勤める時は、成田屋の花紋である牡丹の唐草になります」
長谷川「ところが同じ芝居でも、音羽屋の系統が勤める時には菊の唐草になります。團十郎が勤める時は、牡丹唐草が描かれた大格子の中には河東節連中がずらりと並び、音羽屋の時には菊の唐草で清元連中が並びます。そして、外題も『助六曲輪菊(すけろくくるわのももよぐさ) 』となります。このように歌舞伎は俳優たちの趣向によって創り上げられるのです」
伊藤「そういった役者の工夫、家の芸と結びついた大道具の文様は他にどのような場面で見ることができますか?」
長谷川「例えば『廓文章』の吉田屋ですね。部屋で待つ伊左衛門のところへ座敷を終えた花魁の夕霧が登場する場面で、豪華な襖が1枚、また1枚と開いていきます。この襖にはおめでたい図柄の“梅”“南天”“松”そして“鶴”が描かれると決まっているのですが、どの順番で配置されるかはそれぞれの役者の家によって違っています」
西洋においても文様は建築物にとどまらず、紋章に取り入れられ意味性を纏うことで豊富なモチーフやデザインを生み出してきました。西洋の紋章のモチーフにはその人物の系譜や地位、出自を象徴するものが使われます。
歌舞伎大道具における役者の文様は、美しさや華やかさ、代々続く家の芸を舞台の上で物語っていると言えるのではないでしょうか。

『助六曲輪菊』舞台の赤い大格子下の“腰”に描かれた、音羽屋の菊の唐草。昭和41年に先代の中村勘三郎が出演した時の図案(先代の中村勘三郎は音羽屋の六代目尾上菊五郎に師事。音羽屋の系統の菊の唐草を使った)

歌舞伎文様考
バックナンバー
-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂
『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。
-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様
今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。
-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)
前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)
話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第10回 和事衣裳の文様と色彩
今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。
-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く
今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。
-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様
今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。
-

第7回 旅する「唐草模様」
数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。
-

第6回 役者紋を纏う
俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。
-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様
日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。
-

第4回 “演技する”文様
十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。
-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話
武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。
-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様
歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。
-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース
歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。



