歌舞伎文様考
左より:『堂島救入浜』春好斎北洲画(鎌輪ぬ文様)、『侠詞花川戸』春好斎北洲画(高麗屋格子)、『いろは仮名四谷怪談』杉山秀麿画(菊五郎格子)、『難有御代賀絵』歌川豊国画(三津大縞)、4点とも上方浮世絵館蔵 禁無断転載
役者の人気が生み出した多様なデザイン
家の芸を象徴する「定紋」に対し、役者個人への熱狂や感情移入を加速させたのが「役者紋」です。楽屋着や手ぬぐいなど、くだけた使い方をされることが多い役者紋は江戸庶民の間で大流行しました。好きな役者とお揃いのものを身につけたいというファン心理は現代にも脈々と受け継がれていますが、それが役者の個性をデザインした紋であるところに江戸っ子の粋を感じます。
役者紋は洒落や語呂合わせといった独自のデザインを生み出しました。中でもよく知られているのが「鎌輪ぬ(かまわぬ)文様」と「斧琴菊(よきこときく)文様」ではないでしょうか。
「鎌輪ぬ文様」は、「鎌」「○」「ぬ」の三文字で「構わぬ」と読ませ、荒ぶる江戸っ子の心意気を表しています。もともとは元禄時代の町奴たちが「火も水もいとわず身を捨てて弱き者を助ける」という心意気を宣言するデザインとして身につけたのが始まりだと言われています。一時廃れていたものを復活させたのは七代目市川團十郎です。大柄の文様を染め抜いた着物はおおらかな芸、勇壮な姿と相まって観客を魅了し、爆発的に流行しました。
一方、七代目市川團十郎と同時期に活躍した三代目尾上菊五郎が愛用したのが「斧琴菊文様」です。自分の名にある菊が入った三つの文様を組み合わせ「良き事聞く」と読ませるデザインは、吉祥文様として縁起を担ぐのが好きな江戸っ子に愛されました。
江戸時代は幾度もの奢侈禁止令で庶民が派手な着物を着ることを禁止されていました。ところが中期をすぎた頃から歌舞伎役者が舞台で多様する縞模様がシンプルな洒落着として人気を博します。役者の名前を縞とともにデザインした文様も続々と生まれました。
初代中村芝翫が、四本縞の格子に鐶(かなわ)繋をあしらい「四つの鐶」で「芝カン」と読ませた芝翫縞。
三、五、六の縞を縦横に交差させ「三五六」で三津五郎と読ませた三津五郎縞。
縦三本、横三本の縞に「中」と「ら」をあしらった中村格子。
高麗屋格子は、松本幸四郎が舞台の衣裳で身につけたもので、太い線と細い線を組み合わせたデザインのよさが庶民の間で流行しました。
名前をグラフィカルに表現する文様は世界にもあまり例がありません。暗号のようなデザインを読み解くという行為は、流行を発信する役者と受け手の観客の距離の近さを感じさせます。
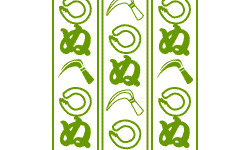
鎌輪ぬ文様

斧琴菊文様

芝翫縞
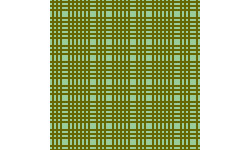
三津五郎縞
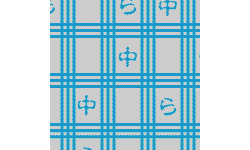
中村格子
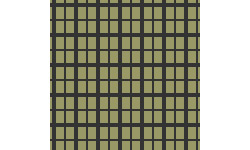
高麗屋格子
歌舞伎文様考
バックナンバー
-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂
『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。
-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様
今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。
-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)
前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)
話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。
-

第10回 和事衣裳の文様と色彩
今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。
-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く
今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。
-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様
今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。
-

第7回 旅する「唐草模様」
数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。
-

第6回 役者紋を纏う
俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。
-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様
日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。
-

第4回 “演技する”文様
十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。
-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話
武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。
-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様
歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。
-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース
歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。



