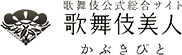昭和57(1982)年、当時大学生ながら初めてアメリカ公演に参加し、これまで計23回53都市にわたる海外公演の大道具装置全般を担当してきた金井大道具、金井社長。なかでも、江戸時代の芝居小屋がニューヨークに登場し話題となった「平成中村座」の準備、立ち上げは、特に印象に残っている経験の一つだそう。また、海外公演で初めて廻り舞台をつくった『NINAGAWA十二夜』など、多くの資料とともに、舞台をつくり上げる現場について語っていただきました。

金井勇一郎(かない ゆういちろう)
市村座の大道具製作を請け負う会社として、明治19(1886)年に創業した金井大道具株式会社、四代目社長。昭和61(1986)年から2年間メトロポリタンオペラハウス(MET)のインターンを経験。平成16(2004)年「平成中村座」で読売演劇大賞優秀スタッフ賞、平成18(2006)年『NINAGAWA十二夜』では、同賞最優秀スタッフ賞を受賞。歌舞伎はもちろん、ミュージカルや演劇など、国内外で幅広く活躍。
インタビュー・文・写真/歌舞伎美人編集部
資料写真/金井大道具
1年前から始まる準備
―海外公演が決まると、どのような準備をされるのでしょうか。
まずは、実際に劇場の下見に行くことから始まります。1年以上前ですかね。下見した劇場にあわせて、道具帖と図面を作成します。それから、出演者や狂言作者、現地の技術担当者とやり取りが始まるわけです。現地とのやり取りは、今ではオンライン会議もできますが、メールもなく、郵送やFAXが中心の時代もありました。そのせいか、現地に着いたら担当者が亡命していて、何も準備ができてないなんてこともあって…大道具は送っていたのでどうにかなりましたが、照明はゼロから準備して仕込んだ経験もあります。
―準備の過程で、日本の公演とは異なることがあれば教えてください。
なんと言っても舞台の間口の違いによることが多いですね。欧米の劇場は舞台間口よりプロセニアムアーチの高さが高いので、間口が横に広い歌舞伎座の舞台構造とはまったく異なります。そこで定式幕は、日本とはまるで違うサイズを3種類ほど持っていて、劇場にあわせて調整します。大道具で特徴的なのは、写真のような松羽目を見ていただければわかると思いますが、間口にあわせながらも、歌舞伎の舞台美術に対して違和感をもたせないような工夫を心がけています。
花道がないこともまた大きな違いだと思います。花道は、現地のスタッフにはイメージがつきにくいものなので、下見の際は一緒になって、花道をどう設置できるか丁寧に検証します。仮設なので消防法に抵触しないようにしたり、劇場の雰囲気に合うように、鳥屋を黒ではなく壁の色にあわせたりなど工夫しています。


―準備で特に苦労することなどはありますか。
毎回、道具の防炎加工でもめていましたね。国によって基準が違うので、合わせるのが大変でした。幕類や造花などの燃えやすいものに、いつも日本で行っている防炎加工をして、日本語の証明書を提出していましたが、当然通用しません。そこで、現地で使用されている防炎剤を調べて取り寄せて、英文の証明書を添付するようにすると、だいぶスムーズになりました。宙乗りで使うワイヤーの強度証明なども必要になりますが、これも現地ですでに承認されているワイヤーや吊り金具などを使っています。
防炎で言えば、現地の舞台の防火シャッターが降りる位置に所作台を設置するときは、所作台の下に鉄骨を置かないといけない決まりもありました。所作台を守るというよりは、煙が出たときに客席にもれないように舞台を密閉する必要があるからです。安全基準は、昔に比べ非常に厳しいものになって大変ですが、大切なことなので細かく対応しています。
海を渡って歌舞伎の舞台をつくる
―準備された大道具は、どのようにして海外へ輸送しているのでしょうか。
大道具は、はじめからコンテナに積めることを想定して製作していますので、でき上がりを確認する「道具調べ」が終わると、ばらしてから船便で1~2カ月かけて現地へ送ります。他に小道具や衣裳など、事前に送ることができる荷物と合わせると、40フィート(約12メートル)のコンテナが通常4、5本くらいになります。芝居小屋のテントをそのままニューヨークへ送ったときはコンテナ32本にもなりました!
―その「平成中村座ニューヨーク公演」(平成16〈2004〉年)で、日本と同じ芝居小屋をもっていくと聞いたときは、どのように感じましたか。
大道具としては、これまでの公演のなかでも最大規模となるため、本当にできるかどうか不安でしたが、このような機会はもうないだろうと興奮したのを覚えています。主催のリンカーンセンターフェスティバル側からも、かつてない規模の公演と聞かされ、公演までに6回は渡米し、下見と打ち合わせを繰り返しました。
公演ひと月前から劇場建設を始めたのですが、レーガン元大統領の国葬とぶつかり、コンテナが1週間遅れて会場に届くなどのハプニングもありました。それでもどうにか予定通りに芝居小屋が完成し、当時人気だったスパイダーマンの映画より面白いという劇評が出た翌日には、チケットは即完売。スパイダーマンの格好をしたお客様も現れました。



―「パリ・オペラ座公演」(平成19〈2007〉年)でも、いろいろな課題があったと聞きます。
この公演は、父・俊一郎が担当し、模型をつくりながら間口の問題や、バレエ用に傾斜がつけられた舞台をどう平らに仕上げるのかなど、関係者とともに熱心に研究したと聞いています。歌舞伎公演と、通常のバレエ公演が交互に行われていたため、花道の設置がかなわず、オーケストラピットの上に舞台を張り出して、そこを十二世市川團十郎さんが弁慶の六方を踏んだことは知られています。その花道も、歌舞伎公演が終わるとばらして、バレエが終わればまた設置したというのですから、考えただけでも大変ですよね。


―『NINAGAWA十二夜』では、幕開きの全面鏡張りが話題となりました。ロンドン公演(平成21〈2009〉年)でも同じ準備ができたのでしょうか。また廻り舞台はどのように再現されたのでしょうか。
ロンドンへも日本で使った鏡を送って設置しました。舞台が日本より狭かったので、鏡に舞台美術が映り込み、偶然にもより幻想的な世界観ができ上がりました。廻り舞台をつくるためには、舞台を1尺(約30センチ)ほど高くする必要があって、一部だけ上げるわけにはいかないので、舞台全体が高くなるよう隅々まで新たな床を敷き詰める作業は大変でした。
また、この公演から新しい取り組みとして、プロダクションマネージャーというポジションを勤めるようになりました。大道具に関する舞台づくりだけでなく、照明、音響、衣裳、小道具、床山など日本サイドのあらゆる要望を、事前に現地スタッフに伝え、調整する役割です。これにより、日本側、現地側で必要なことが事前に共有されましたので、楽屋内から、大がかりな舞台装置まで、到着してからスムーズに作り込むことができました。


海外で求められる力
―プロダクションマネージャーという役割の必要性を感じたのは、以前インターンをされていたという、METでの経験が大きいのでしょうか。
昭和60(1985)年のアメリカ公演に同行していたとき、METから勉強に来ないかと誘われたのがきっかけで、翌年から2年間、文化庁在外研修員としてニューヨークへ留学させてもらいました。当時のMETのテクニカルディレクター、ジョセフ・クラーク氏から多くのことを学び、なかでもバックステージの指揮系統が明確だったことは強く印象に残っていて、歌舞伎の海外公演を重ねながら、その必要性を感じていたところでもありました。多くの専門性が必要となりますが、やりがいのある仕事です。
―現地に到着後、わずか1週間ほどで現地スタッフと舞台をつくりあげていくには、そういった調整力が必要なのですね。数々の公演を通じて、感動した瞬間があればお聞かせください。
それはやっぱり現地スタッフとの協働作業です。国が違えばもちろん言語も違うわけで、作業のやり方、考え方なども違います。最初は衝突もありますが、徐々にお互いを理解し合い、尊重し合い、初日に向かって協力し合う姿は感動します。なので、一番感動する場面と言えば、初日公演後の、現地スタッフとの乾杯です!

―バックステージからご覧になっていて、現地のお客様の反応の違いを感じたことはありますか。
日本の伝統芸能である歌舞伎に対して、古典芸能という認識ではなく、「演劇」という認識をもって観劇されるお客様が多いと思います。現地の劇評に関しては、かなり厳しい目と深い知識をもって、さまざまな角度から執筆されています。「平成中村座」のニューヨーク公演の際、New York Timesで芝居小屋や大道具についても取り上げてもらえて、とてもうれしかったことを覚えています。なぜかLivingの欄だったのですが(笑)。

―最後に、海外公演への思いについてお聞かせください。
学生時代にアメリカ公演に同行したことから、METへ留学することとなり、自分の人生は大きく変わりました。帰国後も、歌舞伎はもちろん、あらゆるジャンルの海外公演を通じて、世界中のさまざまな人々との交流関係が、今の自分の財産です。関わったすべての方に感謝しています。