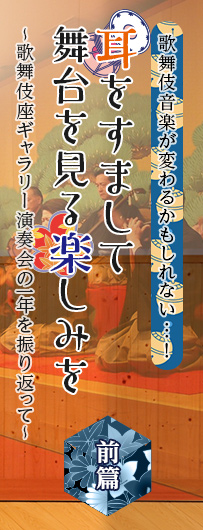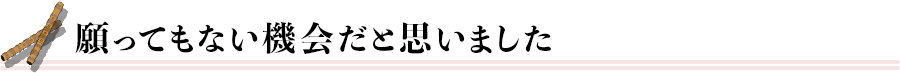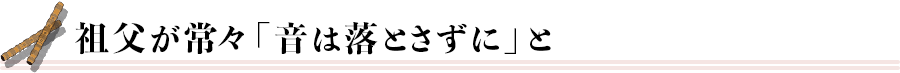【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
竹本葵太夫
(たけもと あおいだゆう)
竹本・太夫
昭和35年、東京生まれ。
昭和51年8月 女流義太夫の太夫竹本越道に入門。
昭和54年7月 竹本葵太夫を二代目として許され、初舞台。
昭和55年3月 国立劇場第三期竹本研修修了。
竹本協会理事長・同事務局長、一般社団法人伝統歌舞伎保存会理事、一般社団法人義太夫協会理事、歌舞伎音楽専従者協議会理事。
杵屋巳太郎
(きねや みたろう)
長唄・三味線方
昭和41年、東京生まれ。
昭和57年 七代目杵屋巳太郎に入門。
昭和59年 二代目杵屋巳吉襲名。菊五郎劇団音楽部に入部。
平成24年12月 八代目杵屋巳太郎襲名。
尾上菊五郎劇団音楽部部長、一般社団法人長唄協会理事。
田中傳左衛門
(たなか でんざえもん)
歌舞伎囃子方、田中流家元
昭和51年、東京生まれ。父は能楽師葛野流(かどのりゅう)大鼓方家元亀井忠雄、母は歌舞伎囃子方田中流前家元九世田中佐太郎。
父、母、八世観世銕之丞、八代目芳村伊十郎に師事、5歳で初舞台。
平成4年1月、七世田中源助を襲名、立鼓となる。
平成16年2月、十三世田中傳左衛門を襲名、田中流家元となる。
歌舞伎囃子協会会長。
昨年9月から歌舞伎座ギャラリーで行われている「歌舞伎座ギャラリー演奏会」が、この11月で14回目を迎えます。これまで出演の中心となってきた竹本葵太夫さん、杵屋巳太郎さん、そしてこの会の“音頭取り”でもある田中傳左衛門さんの三人に聞きました。
取材・文=矢口由紀子 写真=松竹写真室 構成=歌舞伎美人編集部
記念すべき第一回
――演奏会が始まって1年。毎回、大盛況です。
傳左衛門:びっくりしました。初回は20人ほどいらしてくださるかな、くらいに考えていたのですが、ふたを開けてみたらスタンディング状態でした。しだいに毎回いらっしゃる方も出てきて、うれしい限りです。とはいえ、直前の開催日告知になってしまうことが多く、楽しみにされている方には心苦しく感じています。それでも続けられたのは、葵太夫さん、巳太郎さんのご尽力のおかげです。
――この会が始まったそもそもの経緯を教えていただけますか。
傳左衛門:平成中村座のベルリン公演に行った際、ベルリン・フィルハーモニーで若手演奏家がロビーコンサートを行っているのを見たことでした。これは若手の研鑽になる。日本でもやりたいと考えていたところに、歌舞伎座ギャラリーができるとうかがい、ぜひそこで開催をと思って、まず巳太郎さんにお話をしました。
巳太郎:願ってもない機会だと思いました。私たち長唄は、アンサンブルとして一つにまとまる演奏が大事なのですが、将来的にはコンサートマスターや第一ヴァイオリンのように、全体を引っ張る力を身につけなければなりません。けれど、若手にはその経験をする場が滅多にありません。それができる、本当に感謝しかありません。
竹本初登場!(第七回)
――竹本の演奏会は第七回が最初でした。
傳左衛門:当然、竹本の演奏もぜひと思っていましたが、皆さんとてもお忙しい。そんなとき、葵太夫さんが竹本協会の理事長になられたので、若い方も多いし、同じお考えだろうと推測しまして、袖を引っ張らせていただきました。(笑)
葵太夫:もちろん、大歓迎でした。そもそも歌舞伎座ギャラリーができてすぐに舞台を拝見したときから、小さい演奏会をするのにぴったりの空間だと思っていたんです。若手の発表会もいいでしょうし、埋もれかけている狂言の試演のようなこともやりたい。竹本をより知っていただくための講座をやるのもいいのでは、などと考えていました。
葵太夫:そうは考えても、こちらは実行力がないものですから…。傳左衛門さんが始められると知ったときには、さすがの行動力!と(笑)。ただ、竹本は社中を組んでおらず皆が一匹狼です。熱意、意志のある方にどんどん出ていただきたいと思っております。
――毎回、興味深いプログラムですが、出演者含め、どのように選定されているのでしょうか。
傳左衛門:興行の合間にやっていることなので、この月は長唄さんがお忙しい、竹本さんがお忙しいということの調整がまずあります。11月なら葵太夫さんは国立劇場、巳太郎さんは博多座、各地を飛び回っていらっしゃいますから、バランスがとれるようにとご相談させていただいています。1回あたり、お話を含めて30分でと考えています。
2回に分けた『京鹿子娘道成寺』(第二回・第三回)
巳太郎:家元(傳左衛門)は面白いことをお考えで、最初の頃に歌舞伎舞踊の大曲、『京鹿子娘道成寺』や『春興鏡獅子』を2回に分けて演奏するという企画がありましたが、あれはまたやっていただきたいくらい面白かったです。
葵太夫:竹本に関しましては、これだけの至近距離で演奏を聴いていただく機会がありませんので、その迫力を感じていただけるだろうと考えております。それと、元来、歌舞伎義太夫は、たとえば芸術選奨のような場ですと演劇部門になって、音楽部門ではないんです。つまり、いつもは俳優さんがいらっしゃる場所で演奏するのが大前提ですので、演奏だけで聴いていただけることが、まず興味深いと考えております。
巳太郎:そうなんです。歌舞伎座ギャラリーぐらいの大きさでというのが、とても面白いのですよね。
――歌舞伎座ギャラリーという空間が、この演奏会の“鍵”のようです。
巳太郎:我々、長唄はホールでの演奏会や舞踊会で演奏させていただくときは、道具(三味線)を少し変えるんです。とはいえ、ギャラリー演奏会は、歌舞伎長唄を聴いていただこうという趣旨ですので、歌舞伎座で使うままの楽器を用い、唄方の声の出し方もそのままを心がけ、若手にもそう申し伝えております。
葵太夫:私ども竹本は、歌舞伎座4階の幕見席の方にも語りが伝わることが標準になっております。歌舞伎座の空間で通用する太夫に、三味線にならなければ、ということ。ですので、スペースに合わせてどうこうとは考えたことがないんです。
傳左衛門:竹本のそのお考えは初めて知りました。興味深い。鳴物はけっこう使い分けしているんです。そこで、お二人のおっしゃることと共通していると思うのは、祖父(十一世田中傳左衛門)が常々「音は落とさずに」と言っていたこと。音の大きさではなくスケール感を落とさずに、ということだと思い、そう心がけております。こじんまりしたスペースでも、歌舞伎座と変わらず、芸のスケール感は落とさずに音量を調節する。…できているかどうかはさておきですが。
| 回 | 開催 | 演目 | 演奏 |
|---|---|---|---|
| 第一回 | 2015年9月15日 | 長唄『勧進帳』 | 長唄 若手演奏家 |
| 第二回 | 2015年11月16日 | 『京鹿子娘道成寺』(前半) ~恋の手習まで~ | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第三回 | 2015年12月15日 | 『京鹿子娘道成寺』(後半) ~恋の手習より~ | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第四回 | 2016年1月7日 | 『春調娘七種』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第五回 | 2016年2月16日 | 黒御簾独吟選~『黒髪』大薩摩 | 尾上菊五郎劇団音楽部 |
| 第六回 | 2016年3月9日 | 歌舞伎名曲選 『春興鏡獅子(弥生)』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第七回 | 2016年4月14日 | 妹背山婦女庭訓『道行恋苧環』 | 竹本葵太夫 竹本翔太夫 | 鶴澤慎治 鶴澤翔也 |
| 第八回 | 2016年5月17日 | 歌舞伎名曲選『春興鏡獅子(胡蝶)』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第九回 | 2016年6月16日 | 「歌舞伎義太夫のメリヤス」 ?義経千本桜編? | 鶴澤慎治 |
| 第十回 | 2016年7月12日 | 名作歌舞伎黒御簾音楽選『三人吉三・白浪五人男』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第十一回 | 2016年8月24日 | 歌舞伎名作撰 長唄『供奴』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第十二回 | 2016年9月13日 | 歌舞伎名作撰 長唄『元禄花見踊』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
| 第十三回 | 2016年10月20日 | 『花競四季寿』―秋の部― 「関寺小町」 | 竹本葵太夫 | 鶴澤慎治 |
| 第十四回 | 2016年11月17日 | 『仮名手本忠臣蔵』より「裏門の段」 | 竹本葵太夫 | 鶴澤翔也 |
| 第十五回 | 2016年11月22日 | 清元『四季三葉草』 | 清元延寿太夫社中 | 田中傳左衛門社中 |
| 第十六回 | 2016年12月5日 | 歌舞伎名作選 長唄『勧進帳』 | 尾上菊五郎劇団音楽部 | 田中傳左衛門社中 |
歌舞伎繚乱
-

三喬 改メ 七代目笑福亭松喬 襲名披露×大海酒造
大阪松竹座「三喬 改メ 七代目笑福亭松喬 襲名披露公演」で、江戸時代から続く上方落語の名跡、笑福亭松喬が七代目として復活します。師からその名を継ぐのは笑福亭三喬。1年にわたる襲名披露興行の第一歩を10月8日(日)、大阪松竹座で踏み出します。
-

KABUKI by KISHIN 篠山紀信特別インタビュー
始まりは47年前、玉三郎さんの舞台を撮影したこと。以来、俳優の刹那を撮り続けてきた篠山さんの作品が408ページの写真集になりました。掲載されているのは、総勢53人もの歌舞伎俳優の姿。篠山さんだからこそ撮れる、迫力の写真の秘密とは。
-

「耳をすまして舞台を見る楽しみを」~歌舞伎ギャラリー演奏会の一年を振り返って~ 後篇
歌舞伎座ギャラリーの舞台は、第四期歌舞伎座の舞台で使われていた檜板。歌舞伎がたっぷりしみ込んだその場所で、2015年9月、第一回 歌舞伎座ギャラリー演奏会が始まりました。1年が過ぎた今、出演の三人が語ります。後篇も公開!
バックナンバー
-

「耳をすまして舞台を見る楽しみを」~歌舞伎ギャラリー演奏会の一年を振り返って~ 前篇
歌舞伎座ギャラリーの舞台は、第四期歌舞伎座の舞台で使われていた檜板。歌舞伎がたっぷりしみ込んだその場所で、2015年9月、第一回 歌舞伎座ギャラリー演奏会が始まりました。1年が過ぎた今、出演の三人が語ります。
-

歌舞伎座「四月大歌舞伎」新作歌舞伎『幻想神空海』―後篇―
ついに幕を開けた歌舞伎座の新作歌舞伎『幻想神空海』。新しいものをつくり上げるため、開幕ぎりぎりまで力を注いできた過程とともに、歌舞伎座の舞台に広がった唐の世界、妖しの世界をご堪能ください。
-

歌舞伎座「四月大歌舞伎」新作歌舞伎『幻想神空海』―前篇―
新しい歌舞伎座に4本目の新作歌舞伎が登場! 夢枕獏の原作をもとに新たに書き下ろされた新作歌舞伎『幻想神空海』の魅力に迫るスペシャルコンテンツ。舞台が開くまでの表も裏も、そして稽古場の様子もたっぷりお見せします!!
-

京都四条南座『あらしのよるに』中村梅枝 中村萬太郎
ヤギのみい姫とたぷ。「オオカミに比べて見た目の印象が薄いので、ヤギに見えるか心配だった」と梅枝さん。「自分で役をつくっていく部分が多く大変、でも楽しかった」と萬太郎さん。ついに初めて尽くしの舞台が開幕!
-

京都四条南座『あらしのよるに』中村梅枝 中村萬太郎
ベストセラー絵本が歌舞伎に!?いったいどんな舞台になるのか、期待はふくらむばかり。始まったばかりの稽古場で、オオカミのがぶ役、獅童さんにずばり!聞いてみました。
-

京都四條南座「春爛漫、京の舞台に、花開く!」
歴史ある南座で、歌舞伎新世代の花形公演の幕が開きました。前回、熱い思いを語ってくれた尾上右近、中村種之助、中村米吉、中村隼人の四人が、舞台に立っての新たな思いを語ります。
-

歌舞伎繚乱 京都四條南座「春、京都、花形歌舞伎!」
2015年、歌舞伎の新世代が今度は京都で花開きます!これから、ではなくて、「今」を見ていただきたいと、若手花形四人が語ります。