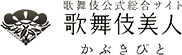紙上で楽しむ歌舞伎
歌舞伎とならんで、海外でも日本文化の粋として親しまれている浮世絵。葛飾北斎、歌川広重の風景画、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿の美人画、そして近年、人気を高めている武者絵の歌川国芳と、江戸の人気絵師たちの作品は、内外を問わず今も数多くの人を魅了してやみません。
そんな浮世絵の半数を占めているのは、実は歌舞伎の舞台や当時の人気俳優の姿を描いた役者絵です。役者絵というと写楽の大首絵がすぐさまイメージされると思いますが、それ以外にも数多くの浮世絵師たちの役者絵が残存しています。このコーナーでは、展覧会などではなかなか紹介されることの少ない役者絵に光をあてて、役者絵から歌舞伎の世界へ皆様をご案内します。

「踊形容柱建てまねび」(おどりけいようはしらだてまねび)
絵師:三代歌川豊国 天明6(1786)年生~元治元(1864)年没
落款:一陽斎豊国画、豊国画、香蝶楼豊国画
判型:大判錦絵3枚続
刊年:安政元(1854)年12月「寅十二」「改」
版元:清水屋直次郎
先般の歌舞伎座「三月大歌舞伎」をはじめとした歌舞伎関連動画の配信は、大きな話題となりましたが、江戸時代、歌舞伎の興行が行われていなかったとき、人々はどのようにして最大の娯楽である歌舞伎に接していたのでしょうか。そんなことをひも解く役者絵を今回は見ていきましょう。
今回紹介するのは、三代歌川豊国の描いた「踊形容柱建てまねび」という作品です。歌舞伎に詳しい方なら、 3枚続の2枚目中央で白扇を持ってきまる、庵木瓜(いおりもっこう)の紋を付けた人物が工藤祐経、その人物を見上げる、むきみの隈をとる前髪の若者の長袴に、蝶の文様が散らされていることから曽我五郎とわかり、この役者絵が『曽我の対面』を描いた作品であることがわかるかと思います。
しかし実はこの作品は、実際の舞台に取材した役者絵ではなく、理想的な配役で描かれた、いわゆる見立の役者絵です。ではなぜこうした見立の役者絵が出版されたのでしょうか。そのわけは安政元(1854)年12月という、この作品の出版時期にあります。出版前月の11月5日、5つ半過ぎ(午後9時頃)、浅草聖天町より出火し、その火はまたたく間に芝居街の猿若町にも及び、中村座、市村座、河原崎座をはじめ、芝居茶屋などを焼き、江戸三座はやむなく休座となってしまいました。
ここからはあくまでも推測の域を出ないお話ですが、浮世絵の出版、販売を商いとする版元にとって、正月商戦の売れ筋商品である初芝居の役者絵を売ることができないのは大きな打撃。そこで、三代豊国に江戸の初芝居の吉例である『曽我の対面』の見立役者絵を依頼し、これを受けて描かれたのが本作品と考えることができるのではないでしょうか。
さて、改めてこの役者絵を見ていくと、工藤が手にする御幣(ごへい)や鏡、三つ扇で飾られた柱は、幣串(へいぐし)と呼ばれるもので、近江と八幡は御神酒と鏡餅を、大磯の虎は曲尺、化粧坂の少将は麻苧(あさお)を、朝比奈は破魔矢をそれぞれ持っています。これらはいずれも柱建て、いわゆる棟上げの儀式に必須の品々です。
ちなみに建築中の建物に最初の柱を建てる“柱建て”と、柱と梁を組み、棟木を上げる“棟上げ”は本来、別の儀式ですが、江戸時代には柱建てに棟上げの意味も含まれていました。
このことから、源頼朝の命を受けて富士の巻狩りの奉行職をつとめる工藤祐経が、狩屋の柱建てを行おうとするところ、曽我十郎が手斧を、曽我五郎がかけや(木槌)を持って、番匠(大工のこと)に身をやつし、工藤のもとに現われて対面を果たす、という発想のもとに描かれた役者絵であることがわかります。
合わせて本作品の画題にもある“柱建て”には、もうひとつの意味があるのではと思われます。それは火事のために休座していた江戸三座の再建工事が、柱建てができるほど進み、歌舞伎の興行が再開される日が近いことを知らせるためのものではなかったかということです。これは、天保13(1842)年の江戸三座の猿若町移転に際して、芝居小屋の棟上げを描いたと推定されている、歌川国芳の「飛騨匠柱立之図」や、三代豊国が芝居小屋の再建の様子をとり上げた安政2(1855)年出版の「江戸花市街建前」といった作品の存在、そして何よりも浮世絵がメディアとしての役割を果たしていたことをふまえると、あながち考えすぎではないように思われます。
芝居小屋の再建と、再び芝居見物ができる日が来ること待ち望んだ人々にとって、今回紹介した役者絵が果たした役割は大きなものがあったことでしょう。そして役者絵を得意とする三代豊国が『曽我の対面』に登場する主要人物に、当時の江戸歌舞伎を支えていた人気俳優をどのように配して描いたかを眺め入り、紙上の歌舞伎を心ゆくまで楽しんだのではないでしょうか。
それぞれの俳優を“曽我の世界”の役に割り当てていき、3枚続の画面の中にバランスよく描きわけていく作業は、まさに浮世絵師の腕の見せどころであり、俳優のニンはもとより、芸風や人気も加味して、実にうまく割り振ってあります。この作品を見ても、工藤の三世嵐璃寛と五郎の二世片岡我童(のちの八世片岡仁左衛門)は、出版当時、立役を代表する俳優であり、近江の四世市川小團次、八幡の三世嵐吉三郎は、その二人に続く実力者。そして虎の初世坂東しうかは立女方、少将の三世岩井粂三郎(のちの八世岩井半四郎)は若女方。十郎の初世坂東竹三郎(のちの五世坂東彦三郎)と朝比奈の初世中村福助(のちの四世中村芝翫)は次代を担う若手花形として頭角を現していました。
安政2(1855)年3月、再興となった江戸三座は相次いで初日を迎えますが、安政年間の江戸は災厄続きで、同年10月2日夜に発生した安政の大地震を始め、大嵐や相次ぐ火災、さらにコレラの流行などに見舞われ、歌舞伎界にも大きな打撃を与えました。しかしそのような社会情勢にありながらも、これにひるむことなく江戸の芝居街は不死鳥のようによみがえり、河竹黙阿弥(当時 二世河竹新七)は、四世小團次と提携し、『十六夜清心』や『三人吉三』など今日に残る名作を相次いで書き下ろし、また観客たちはその舞台に喝采を送っていました。
こうした当時の歌舞伎をとりまく数多くの人々のたくましい活力が、歌舞伎を支える源泉になっていたわけですが、先人たちのそうした姿勢は、現代を生きる我々へのある種のエールのようにも感じられます。