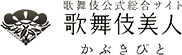顔見世興行、“芝居国の正月” その弐
歌舞伎とならんで、海外でも日本文化の粋として親しまれている浮世絵。葛飾北斎、歌川広重の風景画、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿の美人画、そして近年、人気を高めている武者絵の歌川国芳と、江戸の人気絵師たちの作品は、内外を問わず今も数多くの人を魅了してやみません。
そんな浮世絵の半数を占めているのは、実は歌舞伎の舞台や当時の人気俳優の姿を描いた役者絵です。役者絵というと写楽の大首絵がすぐさまイメージされると思いますが、それ以外にも数多くの浮世絵師たちの役者絵が残存しています。このコーナーでは、展覧会などではなかなか紹介されることの少ない役者絵に光をあてて、役者絵から歌舞伎の世界へ皆様をご案内します。
※画像は、クリックして拡大できます

「木ひき町 森田座顔見勢楽屋之図 三枚続」(こびきちょう もりたざかおみせがくやのず さんまいつづき)
絵師:歌川国貞 天明6(1786)年生~元治元(1864)年没
落款:五渡亭国貞画 (貞三升印)、国貞画、国貞画
判型:大判錦絵3枚続
刊年:文化9(1812)年 「極」(極印)、「鶴金」(行事副印)
版元:西村屋与八
彫師:彫工萩原浪次郎
芝居街(しばいまち)がことさら華やいだ雰囲気につつまれた顔見世興行。“芝居国(しばいこく)の正月”とうたわれた顔見世の様子を、今回も役者絵からひも解いていきたいと思います。
歌舞伎ファンにとって、歌舞伎の舞台のみならず、楽屋の様子も覗いてみたいと思う心理は、いつの時代も変わらないもので、歌舞伎役者の楽屋での姿を描いた役者絵、いわゆる楽屋図が数多く残されています。
今回最初に紹介する作品は、文化9(1812)年11月の森田座の顔見世興行『雪芳野来入顔鏡(ゆきもよしのきごとのかおみせ)』の楽屋の様子を、歌川国貞(のちの三代豊国)が描いた「木ひき町 森田座顔見勢楽屋之図 三枚続」です。
この作品刊行の前年の文化8(1811)年、国貞は中村座と市村座の楽屋図を描きましたが、これが好評を博して、楽屋図ブームが起こりました。こうした背景を受けて描かれたのが本作品で、画題の下に出版の経緯が記されています。
当時の森田座は興行的に苦しい時代が続いており、文化8年は顔見世興行を行うことができず、翌文化9年春まで休座となっていました。
この時代、森田座は木挽町5丁目(現在の東京都中央区銀座6丁目)にあり、堺町(現在の東京都中央区人形町3丁目)の中村座、その隣町の葺屋町の市村座と比べて立地の面でも不利な環境にありました。
起死回生を願っての文化9年の森田座の顔見世は、五世松本幸四郎、五世岩井半四郎、七世市川團十郎、初世尾上松緑を始めとした顔ぶれがそろい、立作者(たてさくしゃ)には四世鶴屋南北を迎えました。
描かれているのは、森田座の楽屋二階と三階部分です。江戸の芝居小屋の楽屋は三階建ての構造となっていましたが、当時は三階建てが禁止されていたこともあり、三階部分を本二階(ほんいかい)、二階部分を中二階(ちゅうにかい)と呼び、表向きには三階建てではないことを装っていました。
ここには描かれていない一階部分には、頭取部屋や囃子部屋、稲荷町(いなりまち)と呼ばれた下回りの役者たちの楽屋などがあり、中二階は女方の楽屋、本二階は立役の楽屋となっていました。ちなみに現在でも幕内では、「お中二階」を女方の異称として用いています。
立役と女方の楽屋を、階をわけて使用するのは、江戸の芝居小屋ならではの特色で、寛延3(1750)年に刊行された歌舞伎の解説書「新撰(しんせん) 古今役者大全(しんせんここんやくしゃたいぜん)」に「江戸芝居の楽屋は三階を立役の部やとす…(中略)…二階を女形の部やとす」と記されていることから、18世紀にはこうした風習が始まっていたことがわかります。
改めて、国貞の3枚続の楽屋図を画面右の1枚目から見ていくと、三階に座元の九世森田勘弥の姿が見え、廊下を挟んだ向かいの部屋には、子役たちに背を向けてくつろぐ、二世常磐津小文字太夫(のちの三世文字太夫)の様子が描かれています。その傍らには常磐津の肩衣(かたぎぬ)が描かれていて、実に心にくいところです。
劇場専属の長唄囃子連中と異なり、常磐津連中は三階の空き部屋を楽屋として使用していたという記録(「賀久屋寿々免」)もあることから、ここは常磐津連中の楽屋と考えて良いのでしょう。
一方、二階に目を向けると、一階からの階段を上がりきったところに、楽屋着姿の名女方の五世岩井半四郎と、その後ろにかつら師の姿が描かれています。このかつら師こそ、羽二重(はぶたえ)に髪を植え込み、これを台金に貼り付けるという、現在の歌舞伎の鬘(かつら)を考案した、友九郎です。
役者絵に裏方の姿が描かれることは多くありませんが、「近来高名のかづら屋」と称された友九郎は、国貞によってたびたび描かれています。友九郎が手にする風呂敷包みのなかには、半四郎のための鬘が入っているのではないでしょうか。
この楽屋図刊行の翌年の文化10(1813)年3月の森田座で、『お染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)―お染の七役』が初演されます。半四郎の七役早替りも、友九郎の鬘の工夫によって実現が可能になったと考えられています。
三階では鬘をかけ、これから衣裳を着ようとする名題下(なだいした)の松本小次郎の姿があり、その前には釜が見え、囲炉裏があることがわかります。この囲炉裏の火は、楽屋がかつて神聖なる部屋であった時代の名残りの“神の火”でした。
囲炉裏の右横、壁に貼り出してある紙には「女中方堅御無用(じょちゅうがたかたくごむよう)」と記して、楽屋への女性の出入りを固く戒めていました。
再び三階に目を戻すと、二世澤村四郎五郎がちょうど鬘をかけていますが、床山が髷(まげ)の部分を持って、これを結い付けようとしています。当時はここで描かれているように、髷の部分が分かれている鬘がありました。
四郎五郎が演じるのは、赤っ面の敵役のようで、支度を手伝う澤村川蔵が刷毛をつかって、紅を塗っています。歌舞伎の化粧に欠くことのできない紅は、この時代、一座の頭取がそれぞれの役者に渡すしきたりとなっていました。