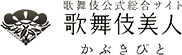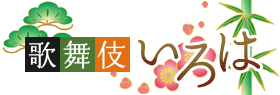
【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。
|
|||||||
富樫佳織の感客道
バックナンバー
-

KIKIさん
雑誌の表紙やCMでおなじみのKIKIさん。建築探訪のエッセイも執筆し、映画やドラマに出演と幅広い活躍をしています。建築やデザインを愛するKIKIさんの目に映る歌舞伎は― 。
-

アダム・エードッシーさん(ブルーマンパフォーマー)
昨年から日本を席巻しているアメリカ生まれのパフォーマンス『ブルーマングループ』でパフォーマーを勤めるアダム・エードッシーさんです。
-

中村七之助さん
今回は特別編として、中村七之助さんに公演に寄せる想い、そして歌舞伎をより楽しむ観方を伺います。
-

種田陽平さん
世話物、松羽目物、舞踊...演目の世界に私たちを誘ってくれる大道具の面白さに注目しながら、日本を代表する映画美術監督の種田陽平さんと観劇をしました。
-

為末大さん
オリンピックという大舞台を経験し続けてきた為末選手の目を通すと、歌舞伎を構築する身体表現に深い意味が重なってきます。
-

美波さん
毎日のドキドキや、観客と一体になる幸せを舞台でいつも感じさせる女優、美波さん。舞台を心から愛するひとが見つめる、歌舞伎の魅力に迫ります。
-

石川次郎さん
今回は、エディトリアル・ディレクターの石川次郎さんと舞台を拝見しました。歌舞伎座の客席に座ったとたん、驚きの事実が明らかに!
-

尾上菊之助さん
今回はロンドンから戻り、東京での凱旋公演に向けて気持ちを新たにする歌舞伎俳優・尾上菊之助さんにお話を伺います。
-

小島聖さん
正統派女優として映画や舞台で凛とした演技を見せてくれる小島さん。みずみずしい感性が歌舞伎と出会ったときに生まれる感動とは。
-

和田浩子さん
経済誌「フォーチュン」による世界で一番パワフルなビジネスウーマン50人にも選ばれた和田さんは、現在、 深く歌舞伎にハマっているのだそうです。
-

ダンカンさん
今回のゲストはお笑いタレント、俳優、劇作家、映画監督と様々な顔を持つダンカンさんです。江戸の破戒坊主をどう見つめるのでしょうか。
-

坂井直樹さん
今回は日産自動車「Be-1」や「PAO」、MOMAの永久保存作品となったカメラ「O-Product」などを世に送り出したコンセプターの坂井直樹さんと歌舞伎を拝見しました。
-

パックン(パックンマックン)
今回はコメディアンとして活躍しているパックンと、時代物の名作のひとつ『盛綱陣屋』などを拝見しました。
-

伊藤正宏さん
『料理の鉄人』などを手がけ、現在も『めちゃ2イケてるッ!』『和風総本家』などの番組で活躍されている放送作家の伊藤正宏さんと芝居を拝見しました。
-

副田高行さん
車のかたちをした緑の葉っぱのトヨタ エコプロジェクトなど、言われたらすぐに浮かぶ印象的な広告を生み出し続けている、日本を代表するクリエイターです。
-

高橋靖子さん
高橋靖子さんは日本のスタイリストの第一人者です。常に最先端を走り続けてきたヤッコさん。一緒に観るならこれしかないと考えていた演目がやってきました。
-

濱口優さん
濱口さんは、芝居が始まると一瞬にしてその世界に没頭します。集中力を研ぎすまして見つけてくれた歌舞伎の楽しみ方 …。するどすぎます。
-

町田康さん
記念すべき1周年の感客は、小説家の町田康さんです。文筆だけにとどまらず、ミュージシャン、詩人、俳優としても幅広く活躍なさっています。
-

川俣正さん
数多くの国際展に参加。世界各地で広場や道路、橋桁の下といった「公共の場」に遊歩道や巨大空間を制作するのが川俣さんの作品です。
-

服部滋樹さん
今回は、大阪・中之島のスペースを拠点に、新しい文化を発信し続けるgrafの代表であるデザイナーの服部滋樹さんに感客となっていただきました。
-

久保純子さん
今回、感客となってくださったのはフリーアナウンサーの久保純子さんです。
-

串田和美さん
独自の世界観で歌舞伎に息を吹き込む串田さんは、どんな目線で歌舞伎を、そしてこの劇空間を感じているのでしょうか。
-

椎名林檎さん
いのちが宿る音をこの世に生み出し続けるひと、椎名林檎さん。彼女は日本人の遺伝子を内包する歌舞伎になぜ揺さぶられるのでしょうか。
-

いとうせいこうさん
編集者、プロデューサー、そして司会者として八面六臂のご活躍をなさっている、いとうせいこうさんと一緒に感劇します。
-

箭内道彦さん(後編)
日本の「現在」をひた走る箭内さんは、歌舞伎にどんなエッセンスを感じるのでしょうか。
-

箭内道彦さん(前編)
日本の「現在」をひた走る箭内さんは、歌舞伎にどんなエッセンスを感じるのでしょうか。
-

オセロ・中島知子さん
今回はテレビや舞台で大活躍中のオセロ・中島知子さんとともに歌舞伎座6月の舞台を拝見しました。
-

書家・紫舟さん
実は歌舞伎を観るのは今回が初めて。伝統文化というフィールドでお仕事をされている紫舟さんの「感客」ぶりが楽しみです。
-

脳科学者・茂木健一郎さん(後編)
自由に歌舞伎を味わう客の心を「感客道」と名付け、観て感じ入る客の道を各界でご活躍されているかたとともに探ってゆきたいと思います。
-

脳科学者・茂木健一郎さん(前編)
「歌舞伎を観てみたい。でも勉強しなきゃいけないんですよね?」としばしば言われます。