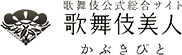紙衣(紙子)
『廓文章』のなかで、散財の果てに勘当をうけた藤屋の若旦那伊左衛門は、紙衣(紙で作った衣)を着て恋人、夕霧のいる吉田屋の店先に現れます。紙衣姿の伊左衛門を見て、廓に来るには相応しからぬ貧乏人とみた吉田屋の若いものが箒を振上げ追い払おうとしますが、吉田屋主人喜左衛門により助けられ、座敷に招き入れられます。そして喜左衛門は、その紙衣姿に同情し、自分の羽織を着せてやります。
この場面では、紙衣は「お金がないから布の着物を買うことができない、紙で我慢せざるをえない」という、零落した伊左衛門の立場を端的に表わしていますが、本当に紙の衣は貧乏人の着る着物だったのでしょうか。
実は紙衣は防寒具として古くから用いられてきました。風を通す麻や綿、絹などと違い、繊維が詰まった紙は暖かいのです。
紙が高級品であった平安時代などには、蚕を殺して得る絹などと違い植物の繊維から作る紙の衣は、仏の教えにも合うということで僧侶に重用されました。室町、戦国時代になると戦のときに寒さを防ぐ衣服として武将達にも用いられますが、江戸時代に入り、紙が庶民の手にも届くものとして普及するとともに、紙衣も身近なものとして着用されるようになっていきます。
丈夫さのために縦横十文字に紙を漉き、繊維の毛羽立ちを押さえ防水効果を得るために柿渋をぬり、手で揉みしなやかさを出した紙は普段の防寒具や旅装用の合羽などに仕立てられました。河竹黙阿弥作『慶安太平記』の≪江戸城外濠端の場≫で丸橋忠弥が着ていた赤褐色の合羽も、実は柿渋を塗った紙衣であったかもしれません。※
助六は喧嘩沙汰を案じる母から、「これを破くような手荒な事はするな」と紙衣を着せられますが、それほど簡単に破れるものでもなかったようです。
絹などに比べれば安価ではありましたが、実際は貧しい人が、やむを得ず着るものでもなかったと思われます。逆に手の込んだものは、絹物より高価なものもあったようです。(み)
※ 台本では"赤合羽"(下級武士、中間などが着る合羽)となっている。
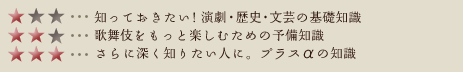
歌舞伎 今日のことば
バックナンバー
-
「蘭奢待」
-
「実盛の白髪染め」
-
「鎧櫃の”前”」
-
「大口」
-
「かんかんのう」
-
「酒呑童子」
-
「江戸のリサイクル」
-
「首実検の扇」
-
「伽羅」
-
「高野聖」
-
「小幡小平次」
-
「六代被斬」
-
「国崩し」
-
「勘亭流」
-
「公平」
-
「東海道四谷怪談」
-
「魚づくし」
-
「善玉悪玉」
-
「旗本奴」
-
「丁半ばくち」
-
「十種香」
-
「伊勢物語」
-
「草薙剣」
-
「紙衣(紙子)」
-
「平敦盛」
-
「三輪山伝説」
-
「道成寺」
-
「青海苔と太神楽」
-
「見立」
-
「三筆・三蹟」
-
「獅子と牡丹」
-
「寺子屋」
-
「水天宮」
-
「お数寄屋坊主」
-
「赤姫」
-
「虚無僧 その2」
-
「虚無僧 その1」
-
「絵看板」
-
「すし屋」
-
「だんまり」
-
「太郎冠者」
-
「屋体」
-
「鬘と床山」
-
「三遊亭円朝」
-
「道成寺もの」
-
「羽衣伝説」
-
「下座音楽」
-
「消え物」
-
「表方と裏方」
-
「在原行平」
-
「秀山十種」
-
「熊谷直実」
-
「夏芝居」
-
「定式幕」
-
「伊達騒動」
-
「朝倉義景」
-
「大薩摩節 その5」
-
「大薩摩節 その4」
-
「大薩摩節 その3」
-
「大薩摩節 その2」
-
「大薩摩節 その1」
-
「時代物と世話物」
-
「シェイクスピア」
-
「松羽目物」
-
「少年俳優」
-
「板付」
-
「ツケ」
-
「大道具と小道具」
-
「俠客」
-
「大名火消」
-
「閻魔と政頼」
-
「浅葱幕」
-
「玄冶店」
-
「江戸の火消」
-
「苧環」
-
「天覧歌舞伎」
-
「揚幕」
-
「拍子舞」
-
「香盤」
-
「仙人の堕落」
-
「ヒーローからヒロインに」
-
「かけすじ」
-
「一幕見」
-
「曾我物の舞踊」
-
「大前髪」
-
「虎の巻」
-
「名題と外題」
-
「土佐派&狩野派」
-
「襲名」
-
「この世のなごり 夜もなごり」
-
「知盛」
-
「幕間」
-
「佐藤継信・忠信兄弟」
-
「権太」
-
「柝」
-
「黒衣」
-
「並木正三 その4」
-
「並木正三 その3」
-
「並木正三 その2」
-
「並木正三 その1」
-
「独参湯」
-
「天狗」
-
「花道」
-
「落窪物語」
-
「屋号」
-
「千穐楽」
-
「見得」
-
「顔世御前」
-
「義経の家来」
-
「山科閑居」
-
「切口上」
-
「岡村柿紅」
-
「鹿ケ谷」
-
「差金」
-
「曾我物」
-
「しゃべり」
-
「川連法眼」
-
「猿若」
-
「戸隠伝説」
-
「玉本小新」
-
「招き看板」